2006 年江苏南京农业大学日语读解与写作考研真题
第一部分 読解(105 点)
次に挙げる三篇の文章を読んで、後の問いに答えなさい。
文章(1)
知覚の役割は、教科書的には、当面の世界の状況を具体的に把握することだと説明され
る。ある日突然、知覚の一つを失ったことを考えると、それはよくわかる。それぞれの知
覚についての教科書的な説明は、だから五感という入力そのものの具体的な説明である。
しかし脳にとっての知覚入力全体の役割は、それぞれ知覚そのものが果たす役割とは、違
うはずである。脳はそうした諸入力の共通の処理装置でもあるからである。ヒトの知覚入
力が脳で究極的に処理されて生じる、最も重要なことは何か。
私はそれを世界像の構築だと考える。われわれはだれでも、ある世界に住んでいると思
っている。その世界では、熱いものに触れば火傷し、火傷するとしばらく痛む。私の家か
らしばらく歩けばお寺があり、休日には何人もの人が写真をとったり、見物しているのを
見ることができる。そこから 20 分も歩けば、鎌倉駅に着く。そこには東京方面と横須賀
方面行きの電車が走っており、少し違った方向へ行けば、
江
え
の
しまでんてつせん
ノ
島電鉄線に乗れることがわ
かっている。
こうした身のまわりの世界像は、動物でも多かれ少なかれ、持っているはずである。た
とえば私の家のネコも、自分の住む世界をそれなりに把握している。それはどうやらお寺
の庭までらしい。そこまで出かけているのは見ることがあるが、それ以上先では、見かけ
たことがないからである。このネコを抱いて、ネコの知っているらしい範囲から出ようと
すると、手のなかで暴れだし、飛び降りて逃げてしまう。
単純な世界像の一つとして、ダニの世界をあげることができる。①葉上にいる吸血性の
ダニは、炭酸ガスに反応して、運動が盛んになる。炭酸ガスの濃度が上がることは、近く
に呼吸をする動物が近づいた可能性を意味するからである。そこにわずかな震動が加わる
と、ダニは落下する。うまく落下すれば、動物のからだの上に落ちる。そこが 37 度程度
の温度であり、あとは
酪酸の臭いがすれば、ダニはただちに吸血行動を始める。(中略)
らくさん
このように、動物がそれぞれの限られた知覚装置から、自己の生存に必要な世界像を作っ
ているであろうということは、ヤコブ・フォン・エキスキュルによって最初に主張されたこ
とである。
われわれヒトが持っている世界像は、はるかに複雑である。しかしそうした世界像がで
きあがるについては、ダニの場合と根本的には同じように、そこにさまざまな知覚入力が
あったはずである。それらの入力は、脳で処理され、しばしば保存される。学校で勉強し
たことも、知覚からの入力である。先生の話を聞けば、話は耳から入ってくる。これは知
�
覚系からの入力である。教科書を読めば、視覚から入力が入ってくる。こうして五感から
入るものを通して、われわれは自分の住む世界がいかなるものであるか、その像を作り出
し、把握しようとする。
このようにして把握された世界は、動物が把握するような自然の世界だけではない。ヒ
トはさらに社会を作り出す。言い方を変えれば、社会はそうした世界像を、できるだけ共
通にまとめようとするものである。ある社会のなかでは、人々はしばしば特定の世界像に
対する好みを共有している。だからその社会は、共通の価値観を持ち、人々はしばしば共
通の行動を示す。同じ社会のなかでも、友人どうしはそうした世界像が一致している場合
が多い。さもないとお互いに居心地が悪かったり、喧嘩になったりする。特定の世界像を
構成し、それを維持し、発展させること、それが社会と文化の役割である。社会はじつは
(
②
)である。
(養老孟司『考えるヒント』筑摩書房による)
問 1 筆者によると、脳にはどのような役割があるか。
A 知覚そのものが持つ働きを使って、世界の中での自分の役割を考えること
B 五感を通して知覚入力し、いろいろなものを見たり、痛いと感じたりすること
C 実際の行動を通して入ってきた知覚により、自分の世界とは違う世界を知ること
D 入ってきた知覚を処理し、自分が住む世界を把握してそのイメージを形成すること
問 2 ネコの世界像について述べた以下の文の中で、正しいものはどれか。
A ネコは世界像を持たず、生活する範囲はかなり広い。
B ネコも世界像を把握しているが、その外側でも生活できるようだ。
C ネコにも世界像が存在し、ほぼその中だけで生活しているようだ。
D ネコは世界像を持っていないが、行動範囲はある程度決まっている。
問 3 ①「葉上にいる吸血性のダニ」が世界像を構築する上でもっとも必要なものは何か。
A 炭酸ガスと震動と 37 度の温度と酪酸の臭い
B 37 度の温度と酪酸の臭いとダニの運動と震動
C 酪酸の臭いと炭酸ガスと動物の呼吸と吸血運動
D 炭酸ガスと 37 度の温度と動物の呼吸とダニの運動
問 4 ヒトとダニの世界像について正しいものはどれか。
A ヒトの世界像の方が複雑だが、他から知識を学んで世界像を作る点は同じだ。
B ヒトの世界像の方が複雑であり、ダニは知覚入力を必要としない点で異なる。
C ヒトの世界像の方が複雑であり、ダニは知覚入力を脳に保存できない点で異なる。
D ヒトの世界像の方が複雑だが、いろいろな知覚を通して世界像を作る点は同じだ。
問 5 ヒトの社会と世界像について述べた以下の文の中で、この文章の内容とあっている
�
も
のはどれか。
A ある社会のメンバーは、それぞれが個別の世界像を持つが、互いの価値観を一致さ
せようとしている。
B ある社会のメンバーは、ある世界像に対して同じような価値観のもとで同じような
行動をすることが多い。
C ある社会のメンバーは、世界像が一致していることにより、互いに居心地の悪さを
感じたり、喧嘩をしたりする。
D ある社会のメンバーは、特定の世界像に対して異なって考え方を持つが、その対立
の中で世界像を発展させている。
問 6 (
②
)に入る最も適当な言葉はどれか。
A 各メンバー固有の世界像
B 脳によって作り出される世界
C 文化を維持し、発展させたもの
D 知覚入力によって把握された世界の状況
文章(2)
若者が転職する理由として、若者の意識の変化や家族関係の変化の影響を指摘する声を
耳にする。若者の仕事に対する考え方や価値観が変わり、昔にくらべ「勤め続けること」
へのこだわりや、それを大事と考える意識が
き は く
希薄になったという。少子化が進展し、親と
の同居も増えてきたことで、親の保護のもとに生活をすることが容易になった、親のスネ
をかじりやすくなったといわれる。その結果、生活のために働く必要も薄れ、転職や失業
を選択することが多くなったというのだ。
たしかに、
若 年 者の意識や家庭環境の変化の影響は無視できないものだろう。しかし、
じゃくねん
若年が転職に踏み切る理由は、本当にそれだけなのか。
①もっと自分から転職や失業に踏み切らざるを得ない別の理由がある。
若者からやりがいを感じられる仕事、誇りや満足を感じることができる仕事に出会える
チャンスが失われつつある。納得のいく仕事に多くの若者が就いていない。そのことが、
会社を辞めることを決断させている。
仕事の中身の変化とあわせて、②仕事量がいちじるしく増大していることも、若者の転
職の背景となっている。多くの企業は「リストラ」という言葉を背後にちらつかせながら
雇用調整を進めている。だが実際には、企業内部の
じんいん
人員整理のむずかしさを反映し、ほと
んどの場合、調整は新規雇用の抑制を中心に行われている。若い社員の立場から考えると、
�
それはいつまでたっても後輩の社員が入社してこないことを意味する。そのため、業務の
末端としての仕事がどんどん増え続ける。何時になっても仕事が終わらない。より高い技
能や知識の獲得へ、会社内のステップアップも期待できない。そんな状況のなか、ある日、
若者は転職を決意する。
転職が増える背景として、会社に余裕がなくなっていることから、若年への企業内教育
訓練であるオン・ザ・ジョブ・トレーニング(OJT)の機会も減っている。自分の能力を
いま働いている会社のなかで発展させるという期待は失われ、結果的に転職志向を強めて
いる。若年のうちでも高卒者の場合、企業内教育の機会が充実している大企業への就職が
きわめてむずかしくなっている。そのことも若年全体についてOJTの減少に
はくしゃ
拍車を掛け、
自発的な転職を促している。
若年の自発的離職の増加は、たんに意識の変化や親のすねかじりだけでは片付けられな
い。しかし、転職の増加をはじめとする若年の雇用状況について、③議論はあまり楽観的
である。若いうちにやりがいのある仕事に出会い、それに取り組み続けることで、仕事に
誇りと責任を感じることができ、それが同時に社会全体の活気を生んでいくしかし、実際
はそれと反対の方向に社会は進んでいる。若年の多くが働く意欲を失い、能力や経験を身
につけていない。それは将来とりかえしのつかない多大な社会的コストを生むことになる。
( ④ )、⑤若年の置かれている深刻な状況についての声が、社会全体に響いてこな
い。若年やブルーカラーの声は、かつてならば労働組合の活動を通じて社会に広く伝わる
ルートがあった。しかし、労働組合の組織率が大幅に低下したこととあわせて、このルー
トは有効に機能していない。かわりに中高年大卒ホワイトカラーといった「日本経済新聞」
などの読者層にかさなり合う人々の雇用に関する不安の声ばかりが、政府やマスコミを通
じて広く伝えられている。
(玄田有史『仕事のなかの曖昧な不安揺れる若年の現在』中央公論社によ
る)
問 1 ①「もっと自分から転職や失業に踏み切らざるを得ない別の理由がある」とあるが、
筆者は若者の利殖をどう考えているか。
A やりたい仕事もない上、働かなくても親と同居すれば生活できるので離職する。
B やりたい仕事を見つけて就職しても、長く勤めることにこだわらないので離職する。
C やりがいのある仕事を与えられても、若年自身の都合で離職を決断する。
D 社会の雇用状況の変化によって、納得のいく仕事に就けずに離職を選択する。
問 2 筆者によると、若い社員の②「仕事量がいちじるしく増大している」のはなぜか。
A リストラによる人員整理で、失業する人が多いから
B 雇用調整でまず対象となるのは新入社員の採用だから
�
C 若い社員の転職が相次ぎ、末端業務が増えているから
D 人員整理の影響で、広範囲の業務をしなければならないから
問 3 筆者は企業内教育訓練(OJT)ついて、どのように考えているか。
A 企業内教育訓練の機会が減ると、もっと能力を伸ばしたいと期待する社員は自発的
に転職してしまう。
B 企業内教育訓練の有無が転職志向に大きく影響するが、それはOJTがいい転職先
を探すために有利だからである。
C 会社に経済的な余裕がなくなると、高い技能を持つ人材の採用が増加し、若年全体
のOJTが減少する。
D 高校卒の若者は大企業への就職をあきらめて、OJTの機会が豊富な中小企業に入
社する傾向にある。
問 4 ③「議論はあまり楽観的である」とはどういうことか。
A 議論は必要ないと思われている。
B 議論が不十分だと思われている。
C 単純な問題として議論されている。
D 重大な問題として議論されている。
問 5 ( ④ )に入る適当な言葉はどれか。
A したがって
B つまり
C そのうえ
D にもかかわらず
問 6 ⑤「若年の置かれている深刻な状況」とは、どんな状況か。
A 社会全体に活気がなく、大企業への就職が難しい状況
B やりがいのある仕事に就けず、会社を辞めざるを得ない状況
C 親のすねをかじりやすくなり、働く必要が薄れている状況
D 若年の自発的離職の増加に社会が無関心な状況
問 7 筆者がこの文章で言いたいことはどれか。
A 若年の声を社会に伝えるために、労働組合の組織率を向上させる必要がある。
B まずリストラによる失業問題が深刻な中高年の雇用不安をなくすべきである。
C 若年の雇用状況はまだそれほど深刻な問題ではないが、社会に伝える必要がある。
D いま若年の雇用状況に目を向けなければ、将来重大な社会問題を引き起こす。
文章(3)
***答えは問題の番号を書いてはっきりと分かりやすく書くこと。***
われわれは環境につよく支配されている。どんなに出家的状況をつくろうとしても、そ
�
こで考えるのに使う言葉そのものが、考えてみれば、環境の一種である。( ① )家も
職も投げうって本当に出家をしたとしても、言葉は簡単に捨てられない。その言葉が出家
以前の残滓をひきずっている。棄てたはずの現実を反映する。それを使うかぎり、心の出
家はできなくなるはずだ。
言葉は事物を表現するために用いられる。反復して頻繁に使われていると、言葉と事物
の両者はいかにも一体不可分のように思われてくる。ことばはもともと記号であって、記
号としての操作ができるはずだが、A事物のくまどりが濃くなると、記号としては自由に
使えなくなってしまう。( ② )。日常の言語で新しいことを考え出したり、純粋の思
考をするのが思いのほか困難であるのはそのためで、科学者は新しい記号をいろいろと案
出する。言葉には二通りの用法がある。一つは事物を指示する使い方であり、他は事物の
関係をあらわす記号としての用途である。具体的用法と抽象的用法と言い換えてもよい。
同じ言葉でも、具体的に用いたり、( ③ )に使ったりする。具体的用法は( ④ )
自然発生であるから問題ないが、それを虚構の記号に見立てるのはすぐれた人間的、
( ⑤ )な営みの成果である。人間が言語的動物といわれるのも、この用法を発達さ
せることに成功したからにほかならない。
具体的に存在するものを指示する言葉を、そういう照応なしに使うようになるこの転換
の教育は思いがけない早い時期に行われている。幼児期のおとぎ話である。
みどり児*は具体的言語を身につけるが、それだけでは直接経験の範囲から出られない。
未知を理解するようになるには、これを虚構化しなくてはならない。存在しないものを表
現した言葉がわからなくては、言語は文化の担い手になることができない。Bそれを理屈
ぬきにやっているのがおとぎ話である。超現実的フィクションであるおとぎ話も繰り返し
語られると、虚構の世界として認知されてくる。こうして、実の言葉に対して虚の言葉が
わかるようになる。( ⑥ )、この虚構化が入念に行われるか、おざなりに通過される
かで大きな違いが出てくるように思われる。虚構化の言葉の( ⑦ )だといってもよ
い。
注:みどり児:生まれて間もない子供
(外山滋比古『知的創造のヒント』による)
問 1
① ・ ④ ・ ⑥ に入る最も適当な言葉を、それぞれ次の中から選び、符号で
答えよ。
A また
B さて
C ただ
D いわば
E かりに
問 2
線部A「事物のくまどりが濃くなる」とは、どういうことか。本文中の言
葉を用いて二十字以内で答えよ。(句読点を含む)
問 3
② に入る最も適当な文を、次の中から選び、符号で答えよ。
�
A 新しい記号を案出できなくなる
B 言葉は環境の一種ではなくなる
C 言葉が事物を全く表現できなくなる
D 思考の手段として扱いにくいものとなる
問 4
③ ・ ⑤ に入る最も適当な言葉を、それぞれ次の中から選び、符号で答えよ。
A 社会的
B 精神的
C 文化的
D 道徳的
E 観念的
問 5 第二段落をさらに二つの段落に分けるとき、後半部分の最初の五文字を抜き出せ。
問 6
線部B「それ」は何を指すか。本文中の言葉を用いて十字以内で答えよ。
問 7
⑧ に入る最も適当な言葉を、本文中から漢字二字で抜き出せ。
問 8 本文の要旨を 100 字以内にまとめよ。
第二部分 作文(45 点)
タイムマシンに乗って私たちは 2026 年にやってきました。あなたはどんな一
日を過ごしていますか。
題目を必ずつけてください。
字数:800~1000 字ぐらい
�
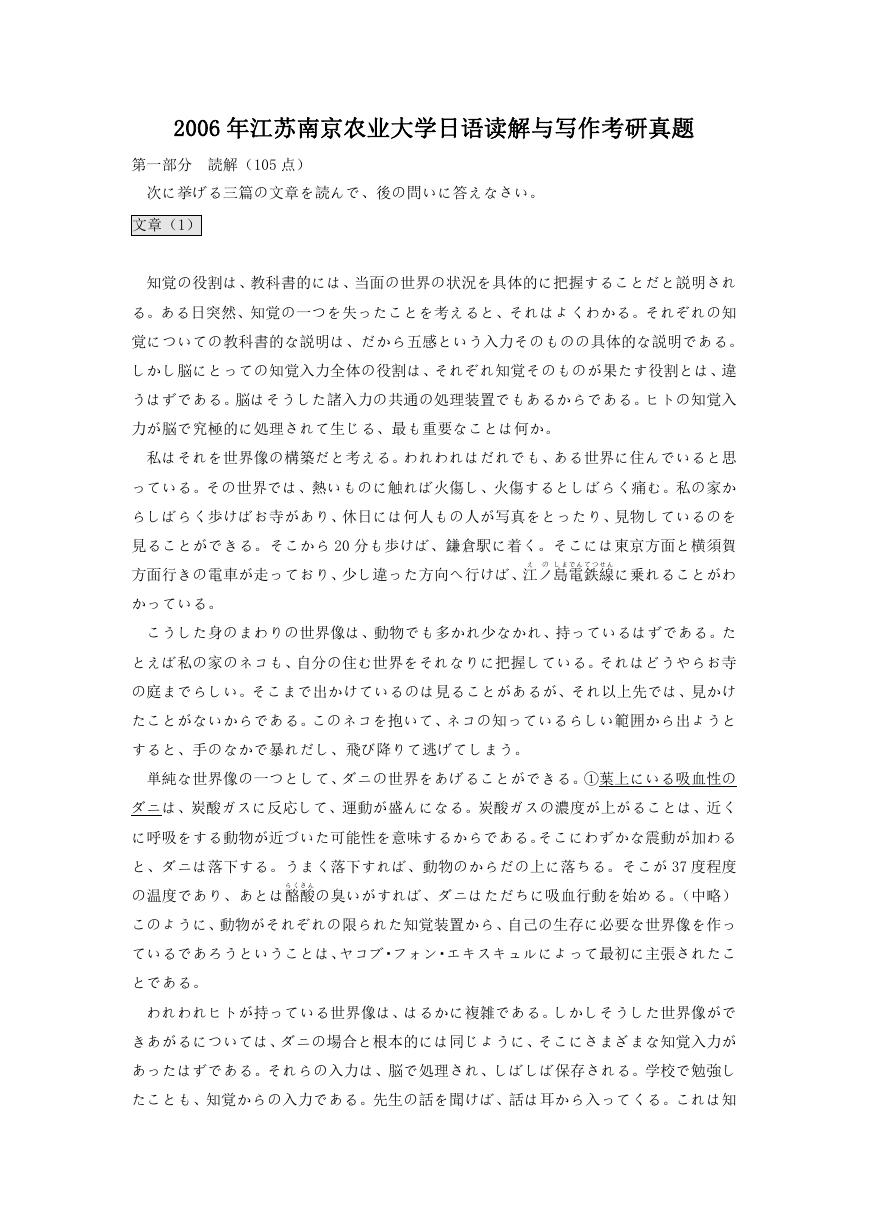
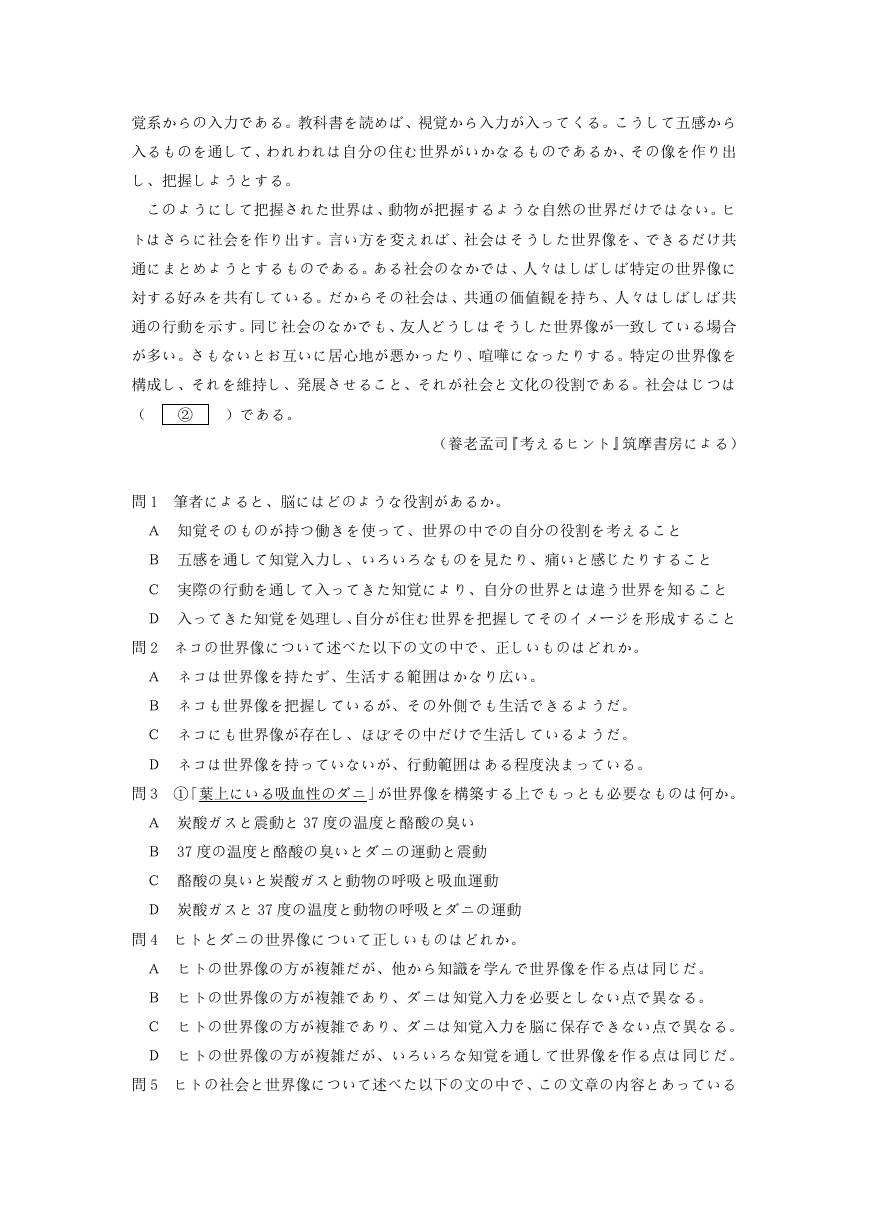
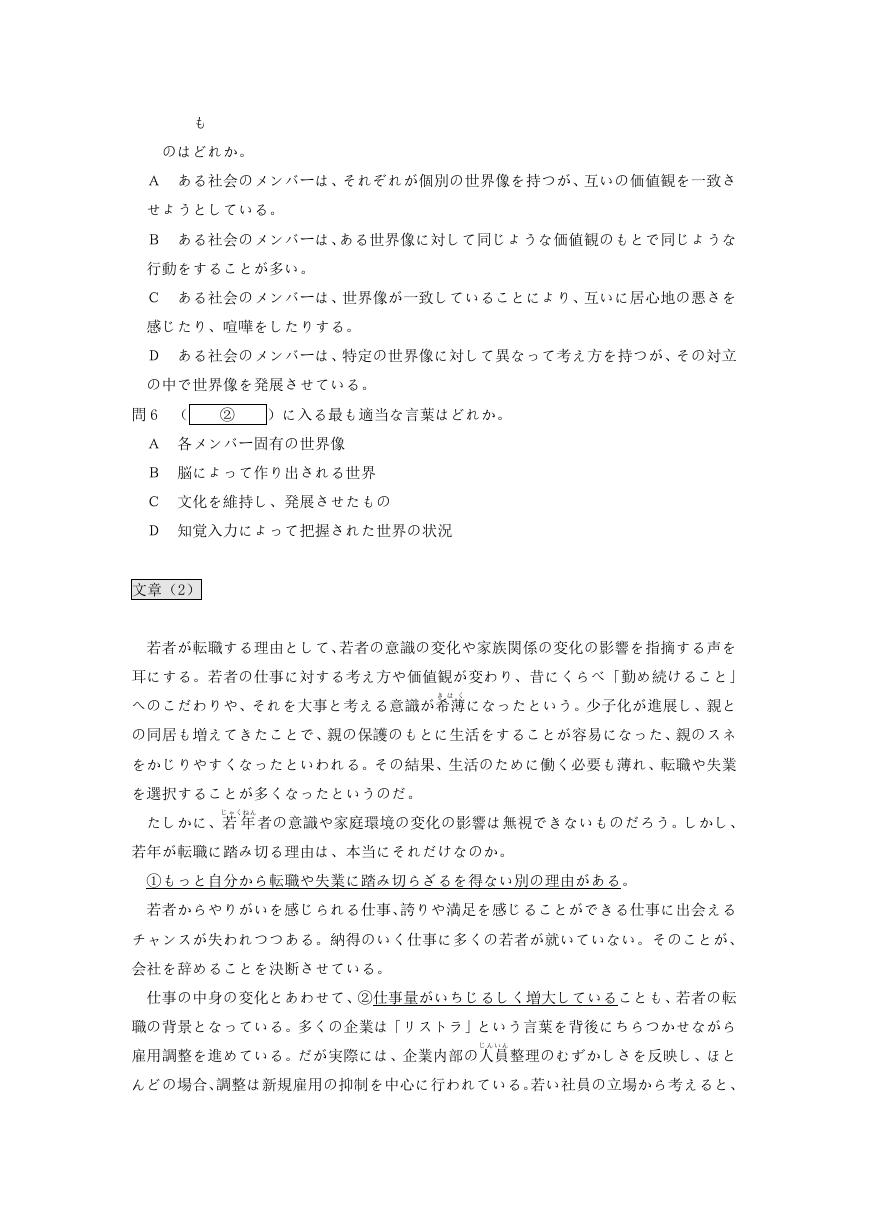
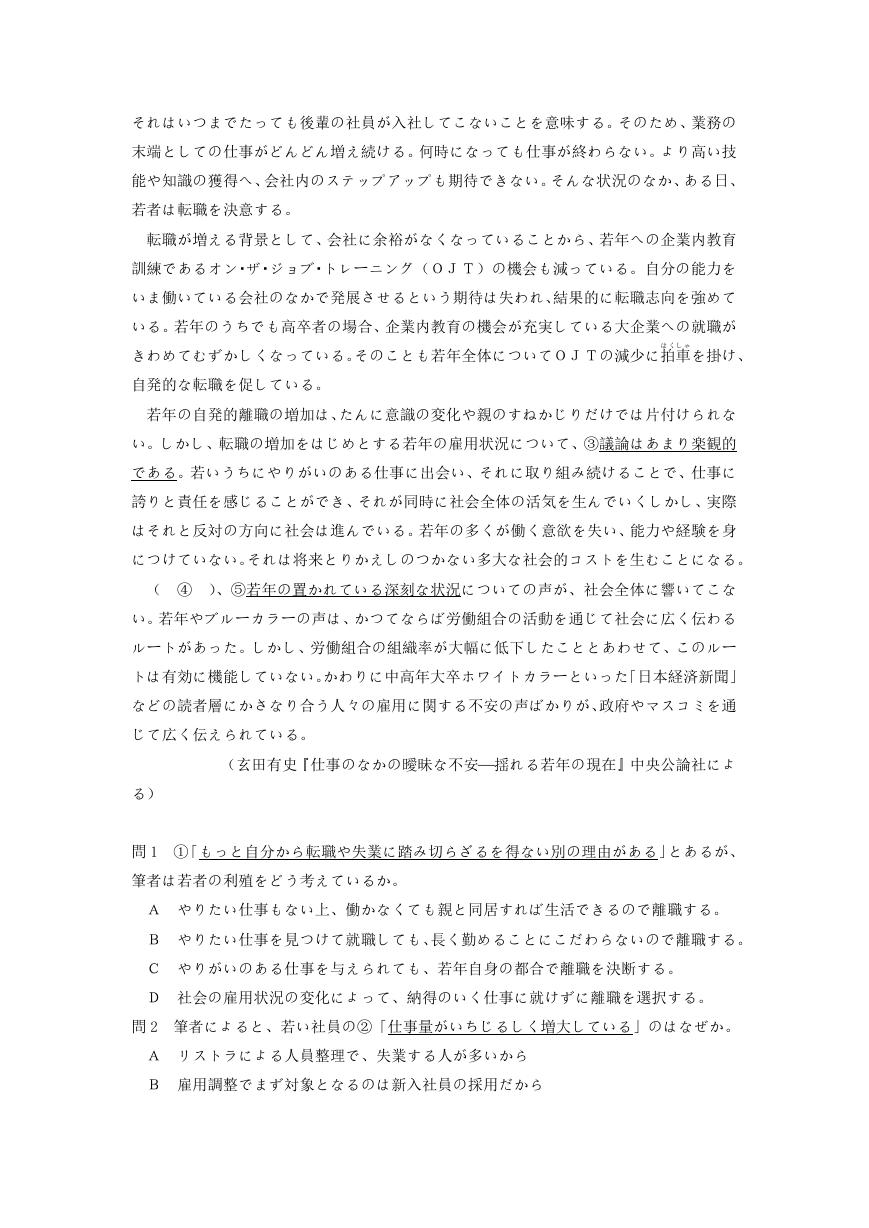
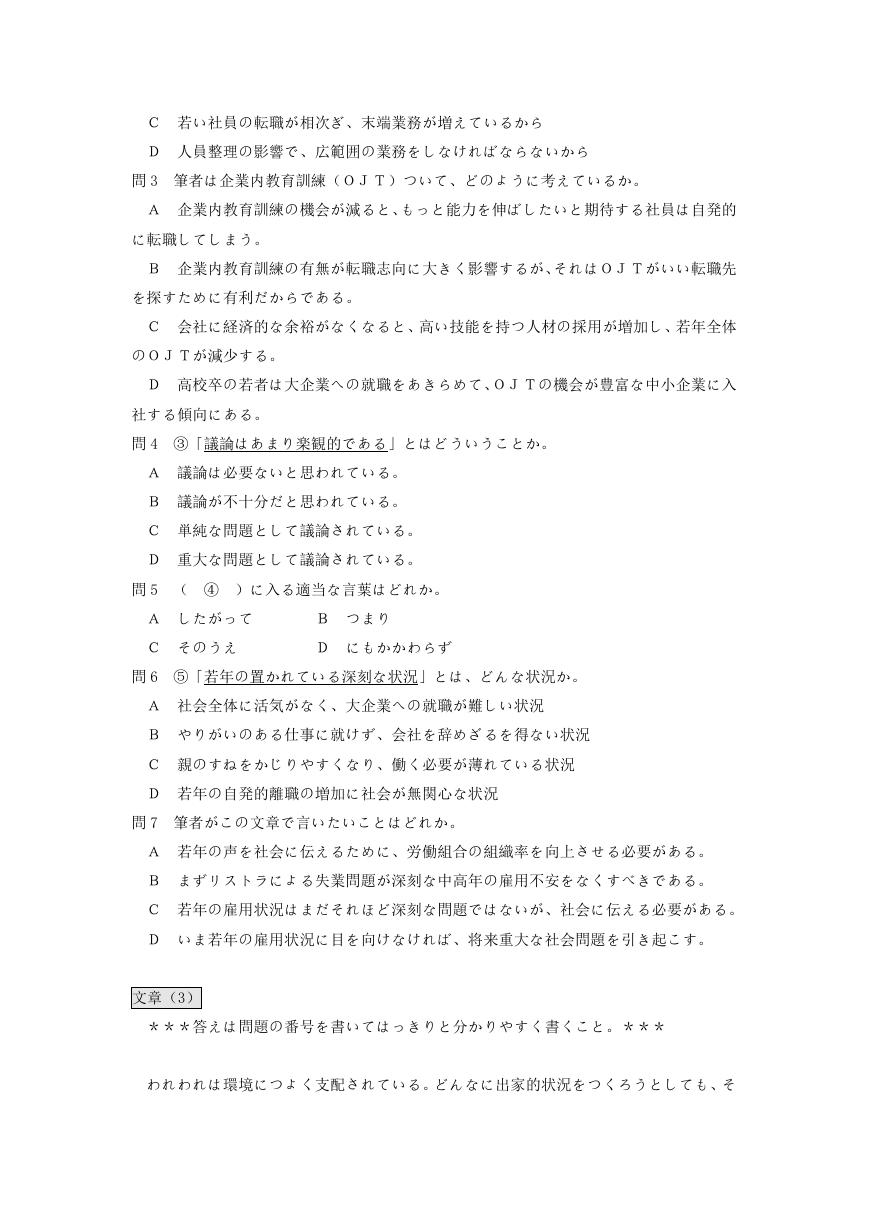

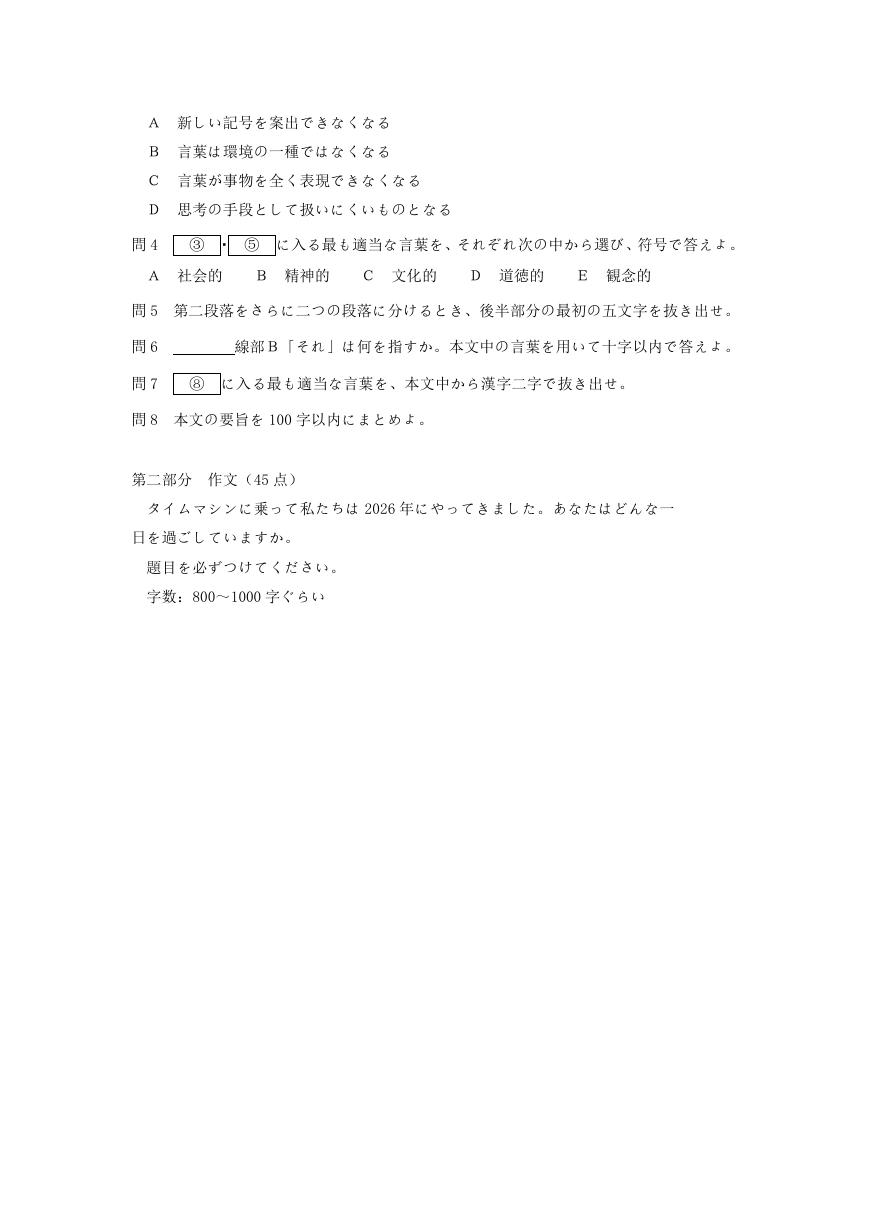
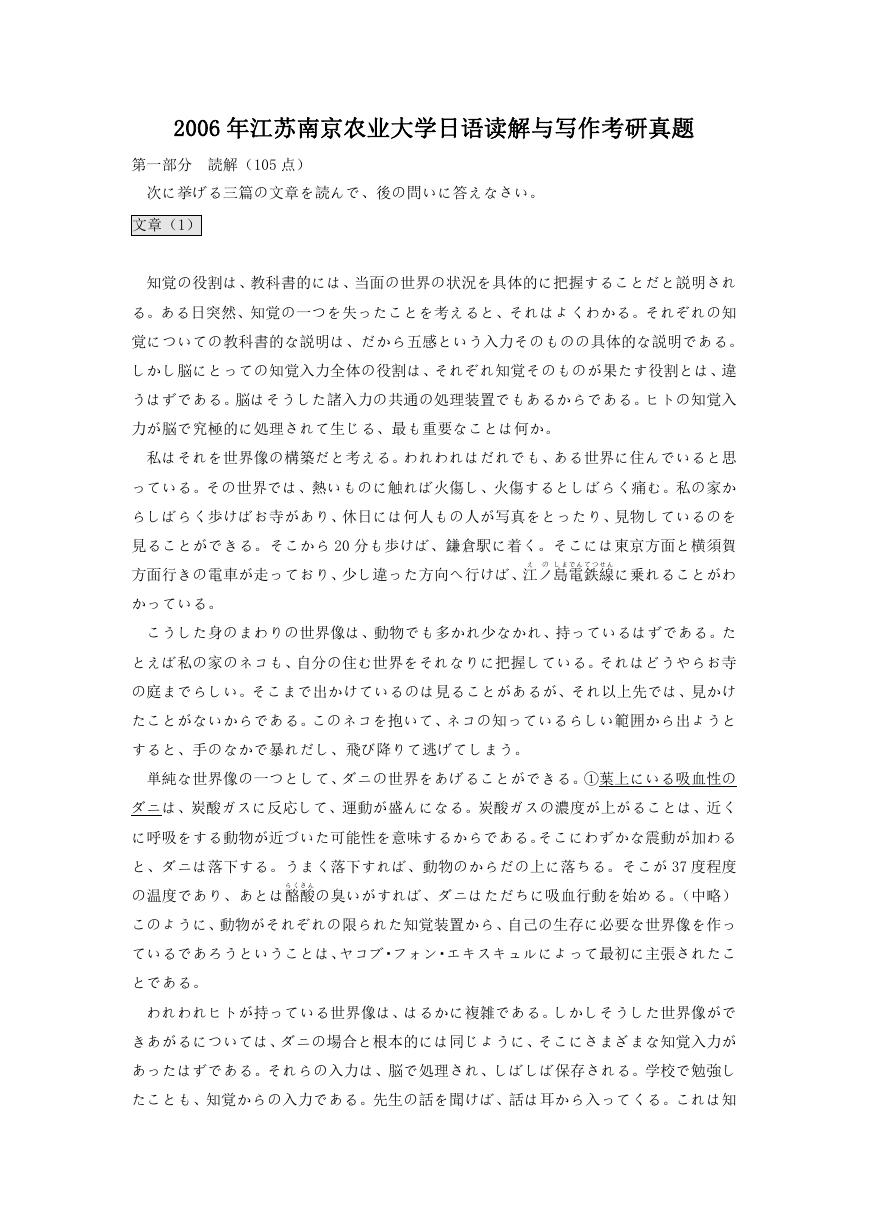
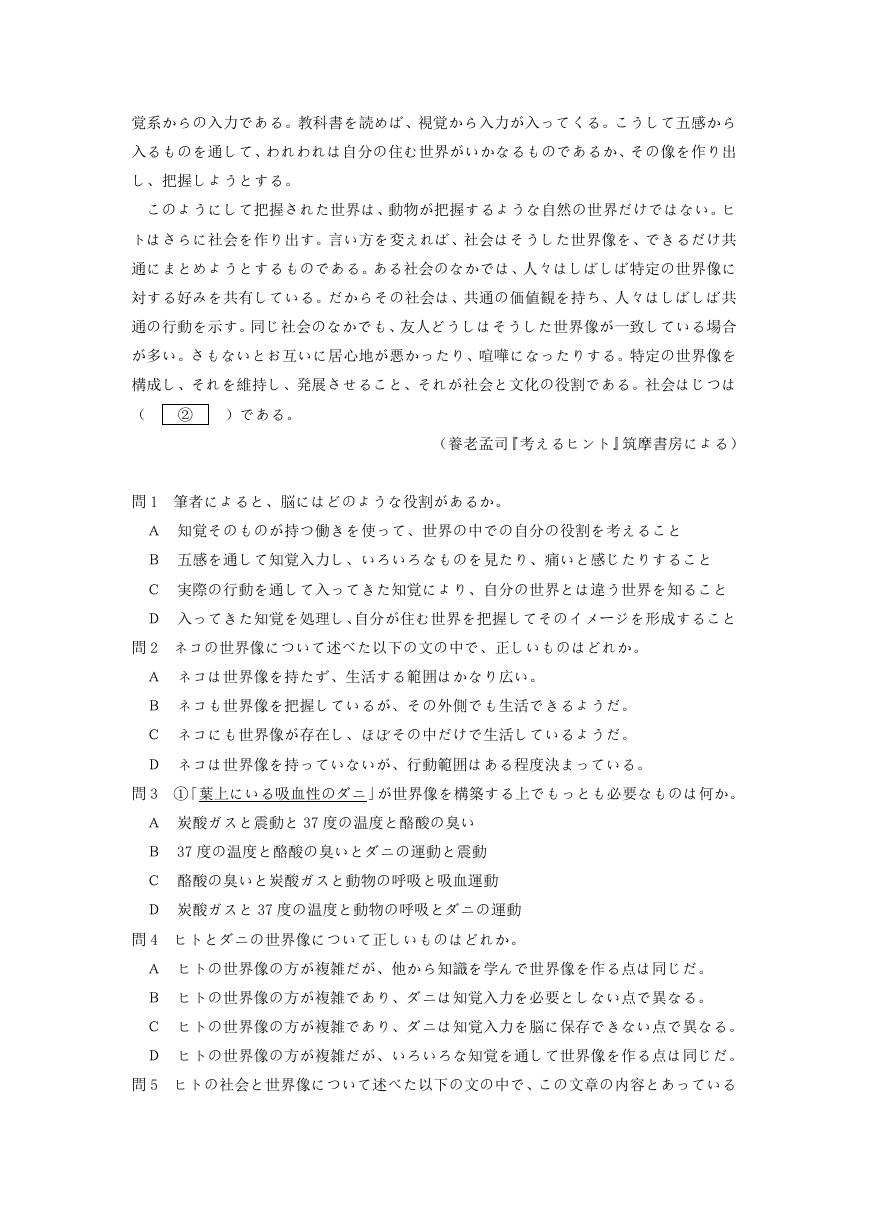
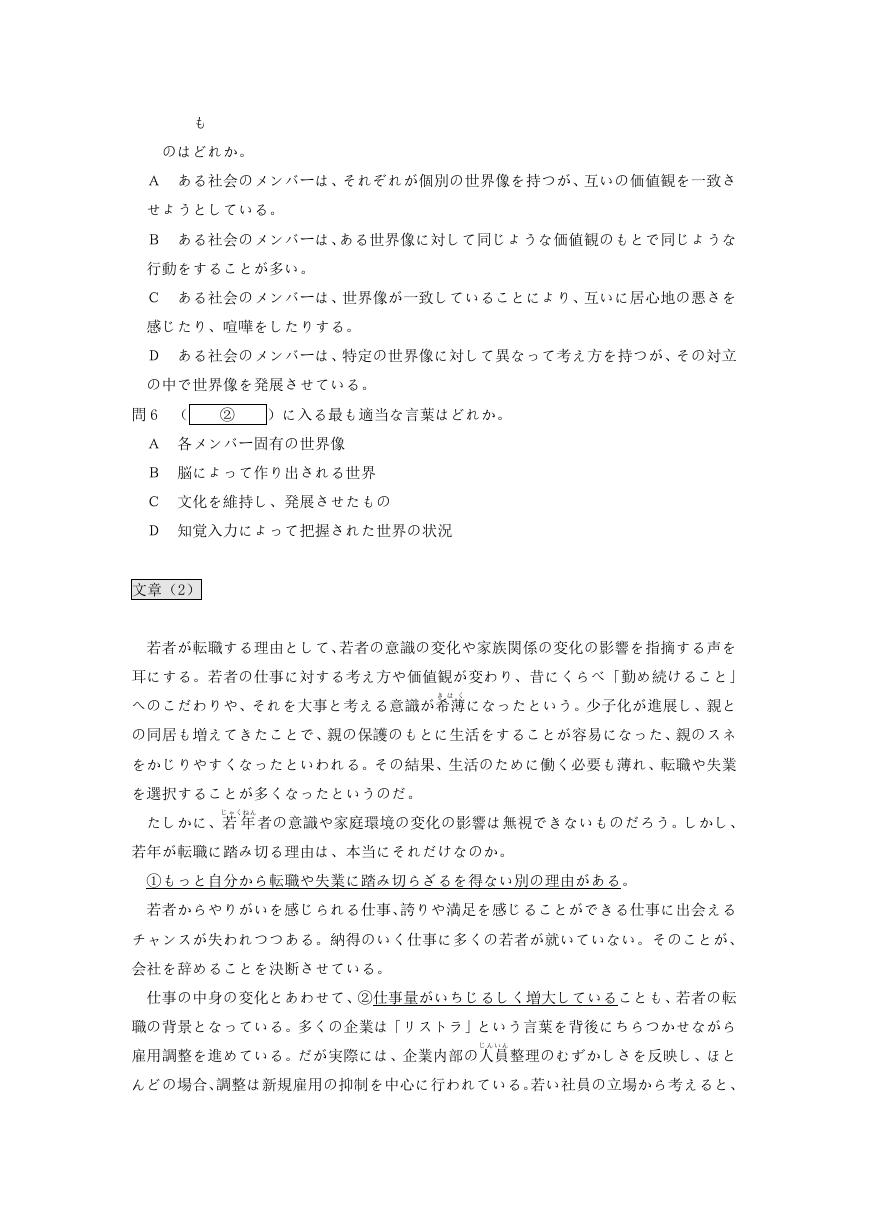
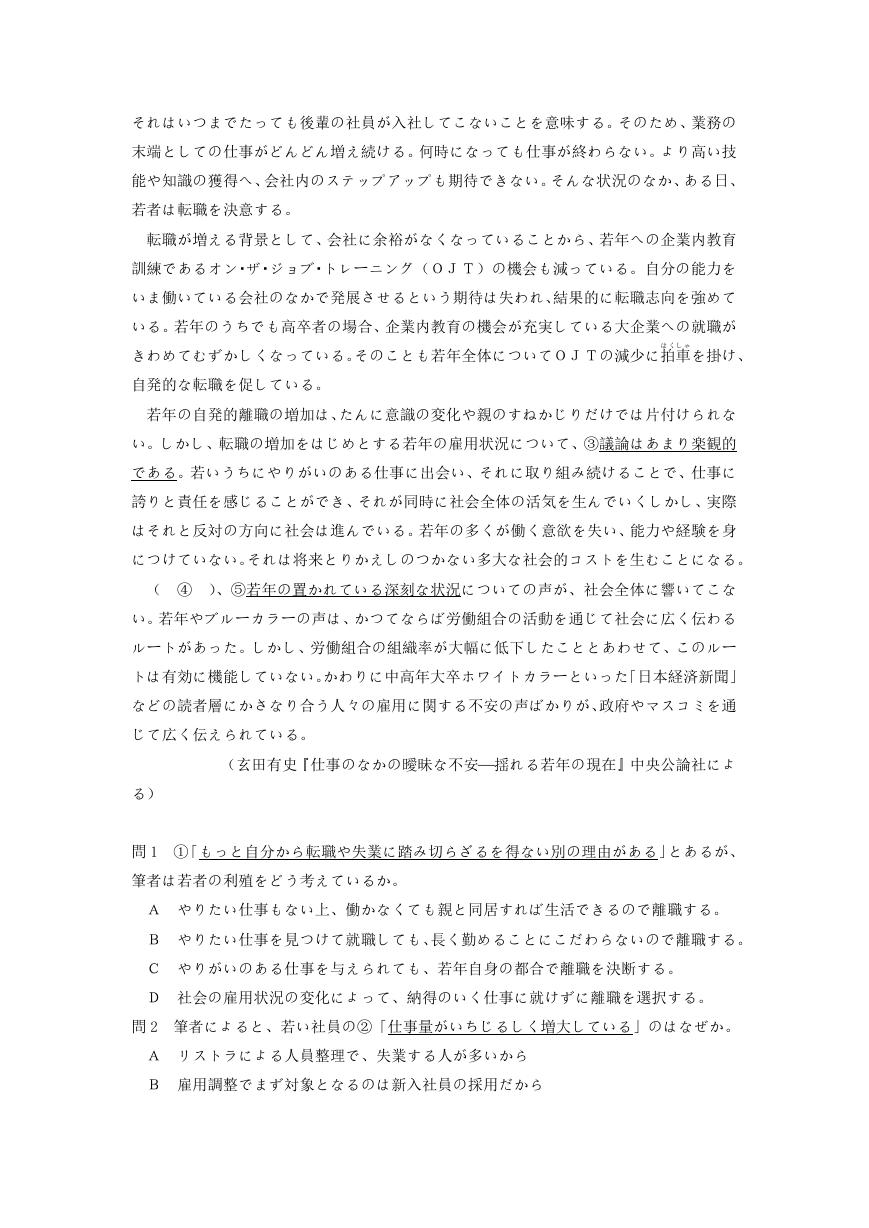
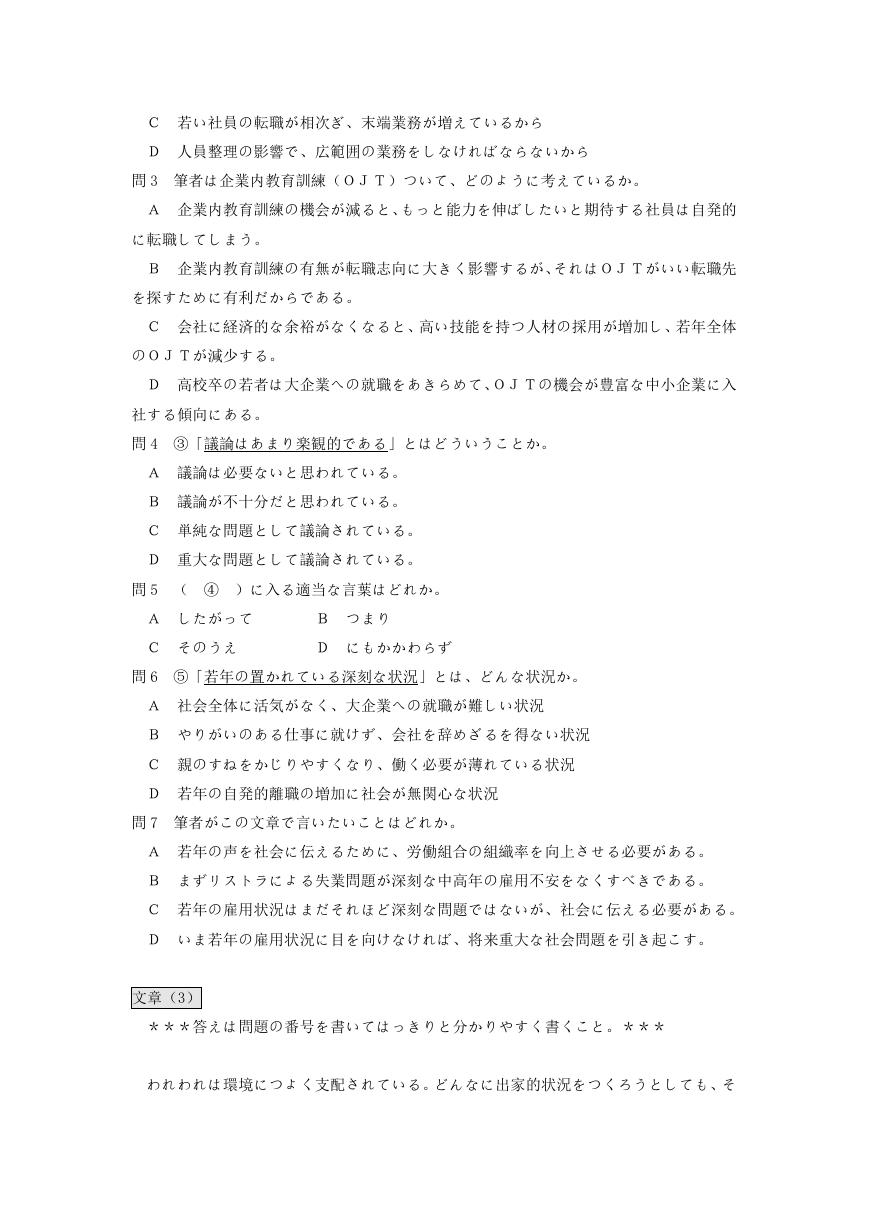

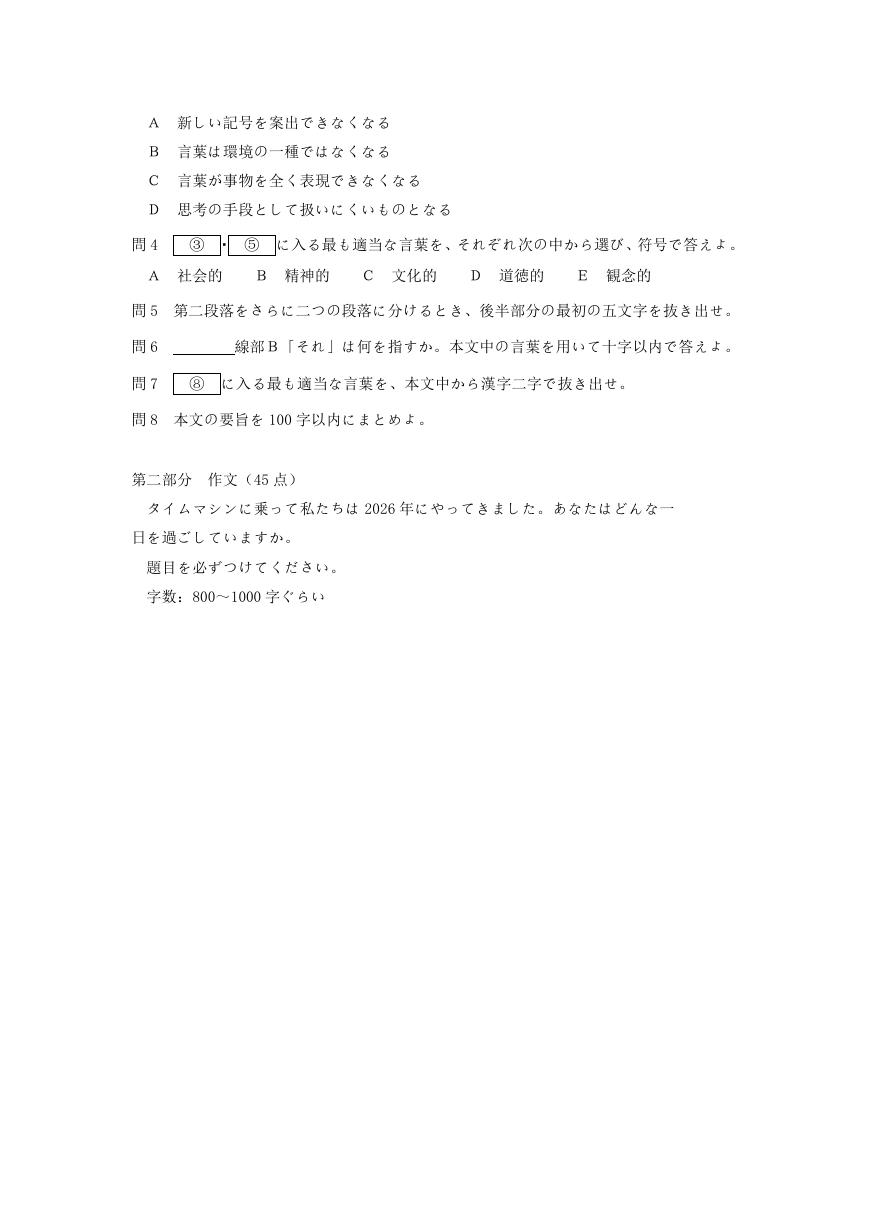
 2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc
2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc
2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc
2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc
2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc
2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc
2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc
2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc
2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc
2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc
2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc
2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc
2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc