2017 年山东青岛大学基础日语考研真题
問題一、次の文のカタカナの部分を漢字に直しなさい。(0.5×20=10 点)
01.彼はメンミツな計画を立て、スポンサーの募集に走り回った。
02.いまは見る影もなくレイラクした。
03.社長の考えの枠をケッシュウしたプロジェクトだ。
04.野生動物をサツリクする。
05.建物を右手の方へまわると、すぐベツムネの離れがある。
06.清らかな水仙の花がイチリンザしに生けてある。
07.運動会はカイセイに恵まれて順調に行われた。
08.あれはおじいさんがタンセイして栽培した胡蝶蘭である。
09.正月だからといって、ハデに集まることもなく、海外旅行に目の色 を変えることも
なくなった。
10.一級試験に通らなくて彼はラクタンしている。
11.さっきからトキオリだしぬけにぱあっと薄日が差してきた。
12.彼は不意を食らって大いにロウバイした。
13.夏はヒショチに行って過ごすのだ。
14.小鳥が朝からコズエに止まってきれいな声で鳴いている。
15.何のヘンテツもない浅い竹のざるが、なんと 1.5 万円もかかるか!
16.この頃、ヨフけになっても眠れない日が多くなった。
17.昨夜のパーティーには胃にモタれないものなんかなかったよ。
18.所詮国民とはムエンの選挙戦だ。
19.社会に害が及んだ、会社創立以来の大フショウジだった。
20.科学技術の進歩にトモナって、生活が簡略化する。
問題二、次の波線部の漢字に振り仮名をつけなさい。 (0.5×20=10 点)
21.老人が山の今昔を話してくれたことがある。
22.パレードをリニューアルする時は、発表されているリニューアル日 の何日か前から
予行演習として新しいパレードのお披露目をする。
23.最終的には何らかの形で敵と妥協し、共存する道を探らなければな
らなかった。
24.右へ左へと転げた拍子に、鉄柱に頭をぶっつけそうになる。
25.孫の卒業式を見届けたいとお祖父さんが言った。
26.粗末な毎日の食事に飽きた。
27.父の店が大変繁盛している。
28.人のものを盗むとは言語道断だ。
29.近くの温泉からは白い湯気が立ち上がっている。
30.話し合いは和やかに進んだ。
31.このころ、懐に金が一銭もなく、困っている。
32.そうした太古の記憶が懐かしいイメージとなって、あの「日本三景」 に結晶してい
るのではなかろうか。
33.友人と改札口で待ち合わせする。
34.祖父の頭は、白髪で真っ白だ。
�
D 世間に対して面目が保たれる
F 知り合いが多い
A 表情を暗くする
B 面目を失わせる
G 顔つきに現れる
H 会う
35.そんな華麗で荘厳な情景を見たら、みな思わず掌を合わせたくなっ
たに違いない。
36.災害地の復興に、日夜、懸命な努力が続けられている。
37.大企業の援助で伝統芸術振興財団が設立された。
38.日本に一年ぐらい滞在する予定だそうだ。
39.京都の観光客は老若男女を問わないわけだ。
40.根気よく障害を排除する努力を重ねて、協定を結ぶことができまし
た。
問題三、次の慣用句の意味を表すものを、a~j から選んでください。
(1×10=10 点)
41.顔が立つ
42.顔が広い
43.顔が潰れる C 頼まれて人に出会う
44.顔に出る
45.顔を合わせる E 世間に広く知られようとする
46.顔を売る
47.顔を貸す
48.顔を汚す
49.顔を曇らせる
I 世間に対して面目を失う
50.顔をそろえる
J 集まるべき人が全員集まる
問題四、次の文の括弧にはどんな言葉を入れたらよいか。1~4 から最 も適当なものを
選びなさい。
(1×30=30 点)
51.資格を取ってから と、就職は難しい。
A.なら
B.でない
C.と思う
D.である
52.幼稚園の先生は子どもに進んで本を読むように 。
A.仕出かす
B.仕向ける
C.仕上げる
D.仕掛ける
53.彼を怒らせたら、それ たいへんだ。
A.こそ
B.でも
C.さえ
D.だけ
54.村井先生は 30 年 英語教師の育成に携わってきました。
A.にわたって
B.にかけて
C.にかかって
�
D.において
55.金というものは、なければ困るが、あれば 、やっかいなもの だ。
A.あったら
B.あったで
C.あるで
D.あるなら
56.この成績では東京大学には 。
A.入るっこない
B.入っこない
C.入らっこない
D.入れっこない
57.本日を 受付を締め切らせていただきました。
A.もって
B.とおして
C.おいて
D.よそに
58.田中さんは、夏休みの旅行 備えて、お金をためている。
A.に
B.を
C.が
D.で
59.最近、疲れているせいか、テレビを のままで寝ることが 多くなった。
A.つけかけ
B.つけっぱなし
C.つけながら
D.つけつつ
60.こんな質問をするようでは、 。
A.よく勉強しなさい
B.自分で考えた方がいい
C.まだまだ勉強がたりない
D.よく勉強したね
61.農薬は農の薬 、使いすぎれば農の毒にもなる。
A.というより
B.むしろ
C.かえって
D.とはいうものの
62.勝てる なら勝ちたいと思うのは人の常です。
A.もの
B.まで
C.わけ
D.はず
63.漢字の第一の重要な性質は、表意性、つまり、ほかの文字と違いま
して、発音を表す 意味も表すということです。
A.と同時に
�
B.に従って
C.につれて
D.に基づいて
64.漢字のそのような性格 、新しい言葉ができた場合に漢字で 書いてありますと意味が
すぐに分かる、といったようなことがあります。
A.なので
B.からして
C.だから
D.からこそ
65.人口の増加 、過剰な土地利用を追求した結果、人の居住地 や耕作地はなぎさのすぐ
近くまで迫ってきた。
A.にともなって
B.からして
C.ながら
D.ゆえ
66.落し物が見つかり 、お知らせします。
A.すぐに
B.とたんに
C.やいなや
D.次第
67.この話は自分が将来、親に 時、子供に伝えてやろう。
A.なった
B.なる
C.なって
D.なろう
68.デパートに行く 行ったのですが、二人でいて何も買えませ んでした。
A.ものは
B.ことは
C.までは
D.はずは
69.この歌を聴くに 、子どもの頃を思い出す。
A.つけ
B.より
C.して
D.対して
70.大丈夫だと言いたい ですが、正直、私も不安です。
A.こと
B.もの
C.はず
D.ところ
71.いくら忙しい 、電話をかける時間ぐらいあるだろ。
A.にせよ
B.においては
C.に先立って
�
D.にしては
72.家族がいる 、どんなに辛い仕事にも耐えられる。
A.からこそ
B.からといって
C.からには
D.からして
73.翻訳は、二つの言語はもとより、それら文化の深い造詣 不可能である。
A.なくしては
B.ないとしても
C.あるとしたら
D.あるとしても
74.防災の名の 、海岸線は松林や砂丘にかわって、コンクリー トの防波堤で固められて
いったのである。
A.したで
B.もとに
C.かわりに
D.ときに
75.あらゆる悪に対する反感が、一分 強さを増してきたのであ る。
A.あたり
B.たびに
C.ごとに
D.おきに
76.さっきから朱雀大路に降る雨の音を、聞く 聞いていたので ある。
A.から
B.ともなく
C.こともなく
D.ともかく
77.私が話しかけたら、あの人はいやだ よこを向いてしまった。
A.とばかりか
B.ばかりに
C.とばかりに
D.ばかりか
78.役人勤めの 、小説を書く。
A.かたわら
B.そば
C.がてら
D.よこ
79.人の忠告を にしてはいけない。
A.ひそか
B.おろし
C.おろそか
D.おもわず
80.働ける 働け。
A.中に
�
B.間に
C.うちに
D.には
問題五、次の文を日本語に訳しなさい。(2×10=20)
81.我觉得在家有在家的好处,可以看电视,去学校有去学校的好处,可
以看很多书挺有意思的。(~は~で)
82.从态度上看,她好像丝毫没有罢休的意思。(からして)
83.这个时候要是对他亲热的话,他就会更加得意,越发不可收拾。(気 を起こす)
84.对于靠写文章才能勉强维持生计的我来说,总是很在意自己文章的好 坏。(まがりな
りにも)
85.京都的人气,不单是靠大龄女青年支撑起来的。京都旅游是不分男女, 老少咸宜的。
(を問わず)
86.不是我有意要说的,说话时不小心对他说了她的事。(はずみで)
87.不要轻易相信那种骗人的鬼话。(眉に唾をつける)
88.要不是你在家里磨磨蹭蹭的话,现在我们已经到了旅馆,吃上美味的 晚餐了。(だろ
うに)
89.从今天开始,二女儿就要参加她的升学考试了。我生怕自己睡过头,从半夜开始,每隔
一小时就会醒来一次。(てはならじ)
90.他点头致意了一下,什么话也没说就走出了房间。(なり)
問題六、読解問題(4+15+21=40 分)
(一)次の文章を読んで、後の問いに答えなさい。(計 4 点)
日本人に、日本語で話せばわかる、通じると思うのも、もしかしたら 幻想かもしれない。
たとえば、「情けは人のためならず」という諺の意味。つねづね人に 情けをかけ、親切
にしていれば、自分が困ったときに誰かが助けてくれ る。だからけっして他人のためじ
ゃない、自分のためでもあるんだよと いうのが今までの解釈だった。しかし、この頃は
違うのだそうだ。あんまり情けをかけると、それを当てにして怠け者になってしまう、だ
から情けはかけるな、ということなのだそうだ。 この解釈があながち間違っているとは
言えないが、時代性というもの だ。現代は食べるのに困るというような人がいなくなっ
てしまった。ど うしても助けなければならないような人がいない。居るとすれば、多く は
その人自身の問題。怠けて働かなかったり、選り好みをしていて仕事
をしていなかったり。そんな人に情けをかけたら、たしかに甘えるだけ かもしれない。言
葉の意味は時代を反映する。
(沖ななも「伝える言葉・感じる言葉」『出版ダイジェスト』1999 年 11
月 20 日)より)
問 1.「情けは人のためならず」という諺の、現在の解釈にあっている のはどれか。(2
点)
A.自分が困っているときは人に甘えたほうがいい。人はみんな問 題があり、助け合って
生きているのだから
B.困っている人を見たら助けてあげよう。自分が困った時に誰か が助けてくれるかもし
れないから
C.困っている人を見ても助けないほうがいい。その人が他人に頼 って怠けるようになる
と困るから
D.困っている人を見たり助けてあげよう。その人が後で必ず自分 に親切にしてくれるか
ら
�
問 2.「情けは人のためならず」という諺の解釈が変わったのはなぜか。
(2 点)
A.怠けて働かない人が少なくなったから
B.昔より人を助ける親切な人が増えたから
C.日本人でも日本語が通じない人が増えたから
D.昔のように助けを必要とする人はいなくなったから
(二)次の文章を読んで、後の問いに答えなさい。(計 15 点)
芥川龍之介の小説( )は、1915 年 11 月『帝国文学』に①掲載。 芥川の真の作家的出
発を告げる初期の傑作である。平安末期の荒れ果て た楼上、職を失った②下人は死人の
髪を抜きとっている老婆を取り押さ えるが、生きるためにはこうするほかはないという
老婆の言葉を聞くや、 その着物を剝ぎとって闇の中へ消えてゆく。材を『今昔物語集』
に取り、下人の心理の推移をみごとに描きとってみせたこの作品の主題をエゴ イズムの
③剔抉に見るか、老婆の語る倫理を超えたニヒリズムに見るか、 あるいは下人の示す善
への勇気と悪への勇気をともに持った人間存在 の矛盾そのものの④凝視に見るか、その
主題は幾様にも読みとれるが、 いずれにせよ人間をつねに複眼的にとらえ、人生の一局
面をあざやかに 切断して作品化せんとする短編作家芥川のまぎれもない誕生をここに
読みとることができよう。
問 1.( )の中の作品名を次の中からひとつ選びなさい。(2 点)
A.鼻 B.地獄変 C.羅生門 D.杜子春
問 2.下線部①~④の単語の読み方を書きなさい。(4 点)
①掲載
②下人
③剔抉
④凝視
問3.次の文章を中国語に直しなさい。(9 点)
どうにもならない事を、どうにかするためには、手段を選んでいる遑
はない。選んでいれば、築土の下か、道ばたの土の上で、饑死をするば
かりである。そうして、この門の上へ持って来て、犬のように棄てられ
てしまうばかりである。選ばないとすれば――下人の考えは、何度も同
じ道を低徊した揚句に、やっとこの局所へ逢着した。しかしこの「すれ
ば」は、いつまでたっても、結局「すれば」であった。下人は、手段を
選ばないという事を肯定しながらも、この「すれば」のかたをつけるた
めに、当然、その後に来る可き「盗人になるよりほかに仕方がない」と
云う事を、積極的に肯定するだけの、勇気が出ずにいたのである。
下人は、大きな嚔をして、それから、大儀そうに立上った。夕冷えの
する京都は、もう火桶が欲しいほどの寒さである。風は門の柱と柱との
間を、夕闇と共に遠慮なく、吹きぬける。丹塗の柱にとまっていた蟋蟀
も、もうどこかへ行ってしまった。
(三)次の文章を読んで、後の問いに答えなさい。(計 21 点)
①このごろ、サラリーマンにノイローゼが多いのは、見ていると、み
んな人のせいにするんですね。なんでも人のせいにする。たとえば自動
車を十台売ってこいというと、十台売れる方法を教えてくれといいます。
そんなもの自分で考えろというと、あなたは②上役としての資格がない、
上役というのは教えてくれるものではないのか。ここへ行って売れば売
�
れるよと、その場所に連れていってくれるものじゃないかといいます。
会社はそんなのんびりしたものじゃないよというと、びっくりしていま
す。つまり、与えられたものをマスターすることなら私はよくできます
といいます。会社は私をちゃんと試験して採用したんじゃないかといい
ます。
これは東大教授から聞いた話ですが、ある学生が、ドイツ語かなにか
で落第点をつけられたら、③教官室へやってきてどなったそうです。④
横で聞いていると、その学生は「私が休んだというならさておき、半分
以上出席した。半分以上出席して、なおかつドイツ語が五十点以下であ
ったのは⑤教え方が悪いのである。」といったそうです。えーつ、⑥反
対じゃないかと思うんですけれどね。ちゃんと出ていてわからないやつ
は、何を聞いていたんだと思うんですけど、学生の言い分はちがいます。
半分以上は出席して聞いていたのに、四十九点になるというのは先生の
責任である。それで先生が「おまえは聞いてなかったのだろう」というと、
「いや聞いていました。だいたい、東京大学の入学試験要項には、東大
の勉強がマスターできる能力があるかどうか調べると書いてあるじゃ
ないか。東大の授業についていけると認定して私を入学させた責任があ
んたにはある」といって頑張り通した。後はどうなったか聞きませんで
したが、これは会社の中でも同じですね。うちの会社の上役は無能だと。
私が十台売れるようにしてくれてないといっているわけです。全部人の
せいにしているわけです。売れるような車をつくってないとか、シーマ
のような車なら売ってみせるとか、なにしろ全部人のせいにしている。
これが不幸になる第一歩です。
上役のせいもあるでしょうけれど、しかし、自分のせいとして受けと
めていくほうが、心は健全になる、力強くなる、能力も進歩する。⑦末
路が哀れにならない、ということをいいたいわけです。
(財団法人精神分析学振興財団編「企業と転勤」『職場と心の健康 4』東
海大学出版会より)
問 1 ①「このごろ、サラリーマンにノイローゼが多い」のはなぜだと筆
者は考えているか。(3点)
A.無理な要求をする上役が多くなったから
B.他人になんとかしてもらおうと思うサラリーマンが増えたから
C.不幸なサラリーマンが増えたから
D.能力が進歩しないサラリーマンが多くなったから
問 2
②「上役としての資格」の内容は何か。(3点)
A.のんびりと仕事ができること
B.部下の気持ちを考え助けることができること
C.仕事のやりかたを具体的に指示することができること
D.採用した責任を果たすことができること
問 3
学生が③「教官室にやってきてどなった」のはなぜか。 (3点)
A.落第点をつけられて困ったから
B.まちがえて落第点をつけられたと思ったから
�
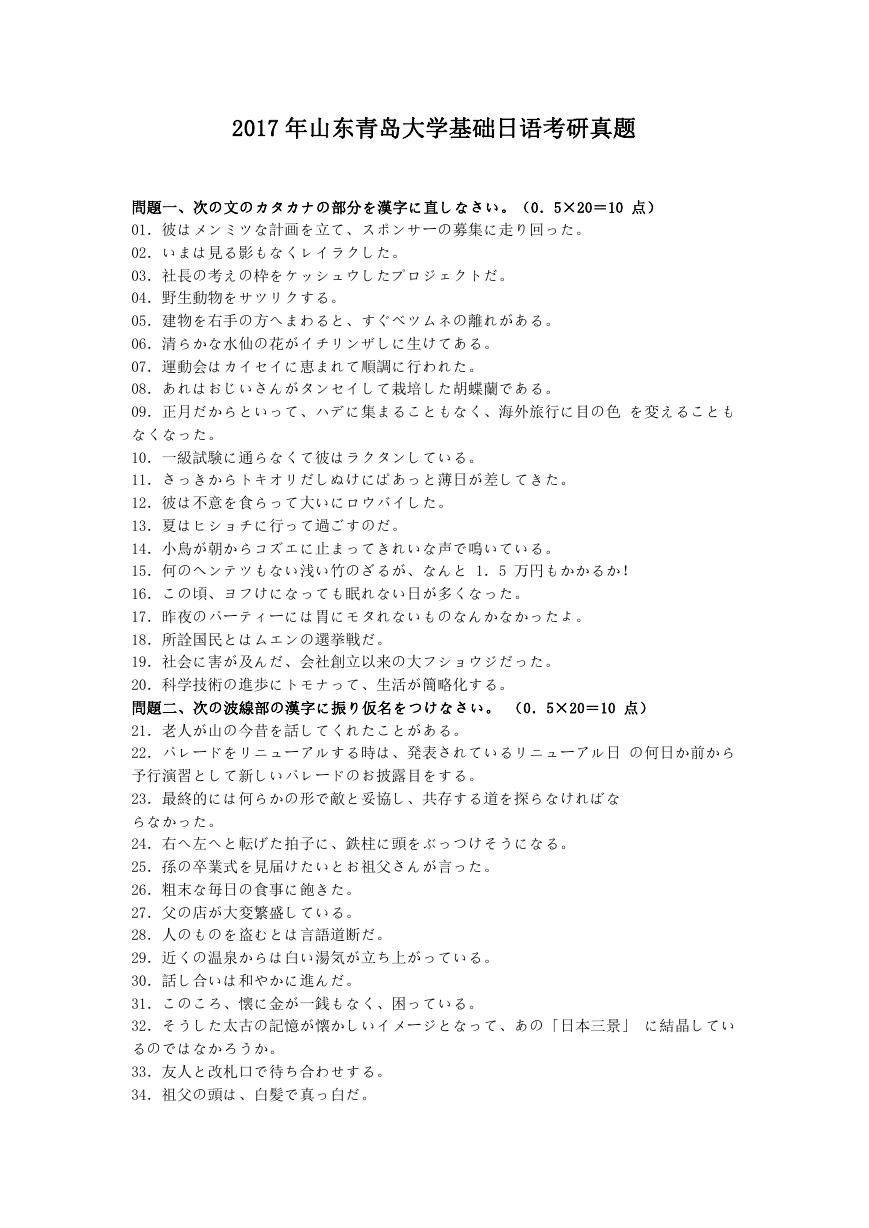
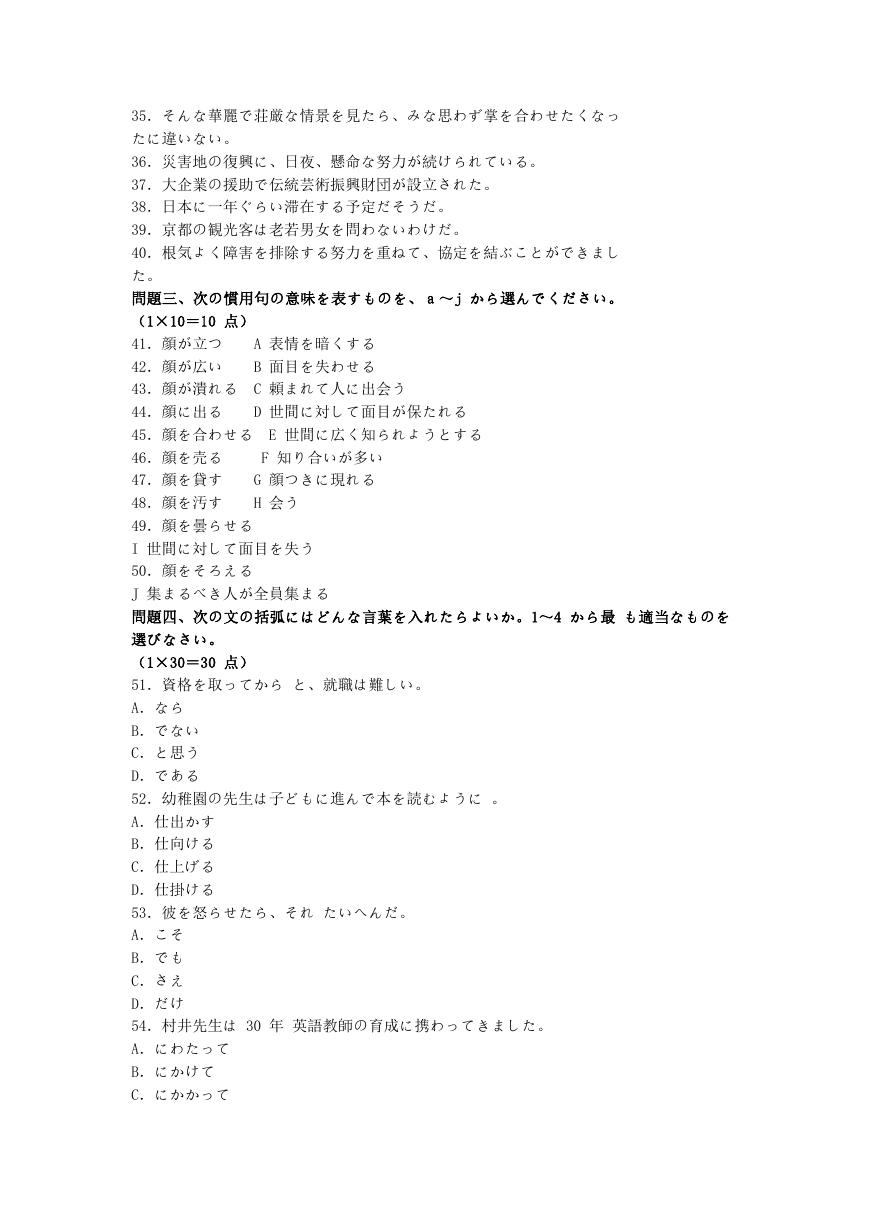
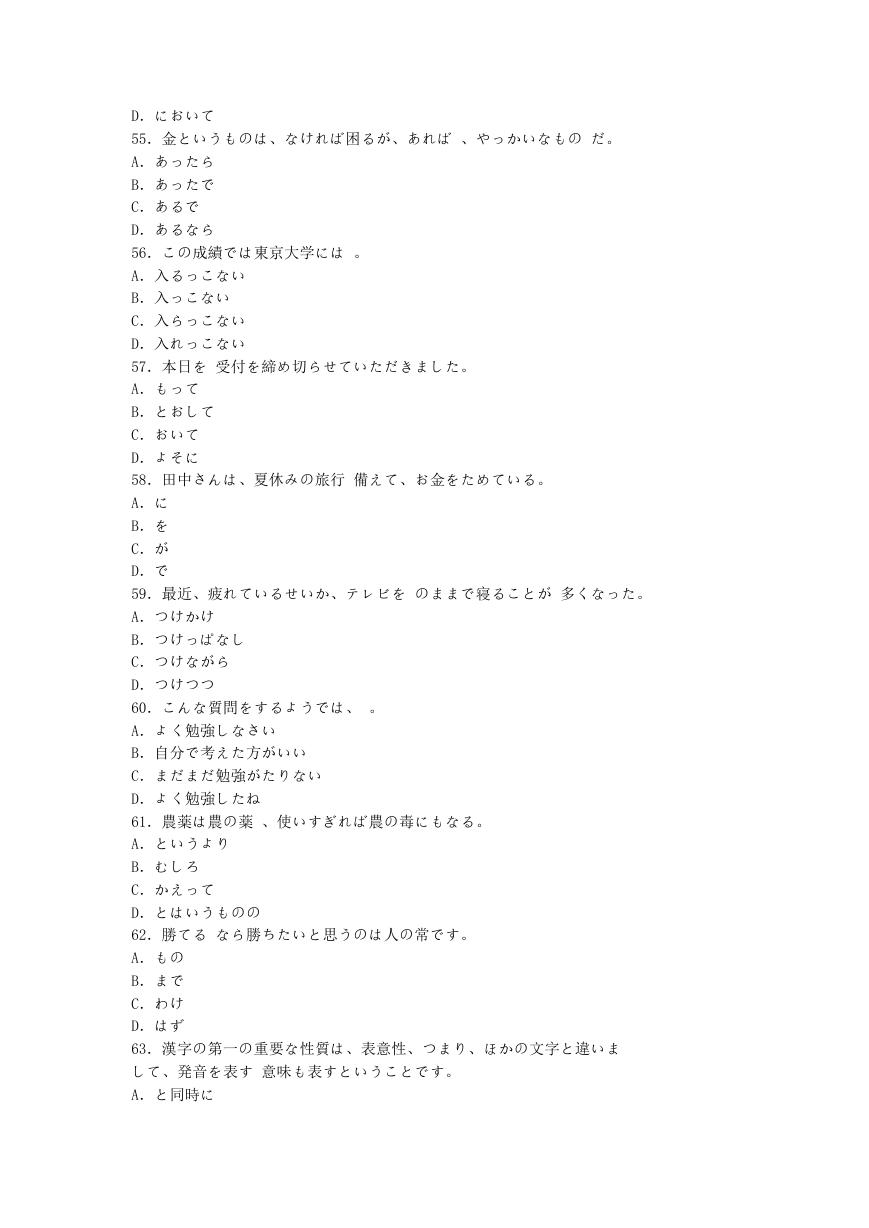
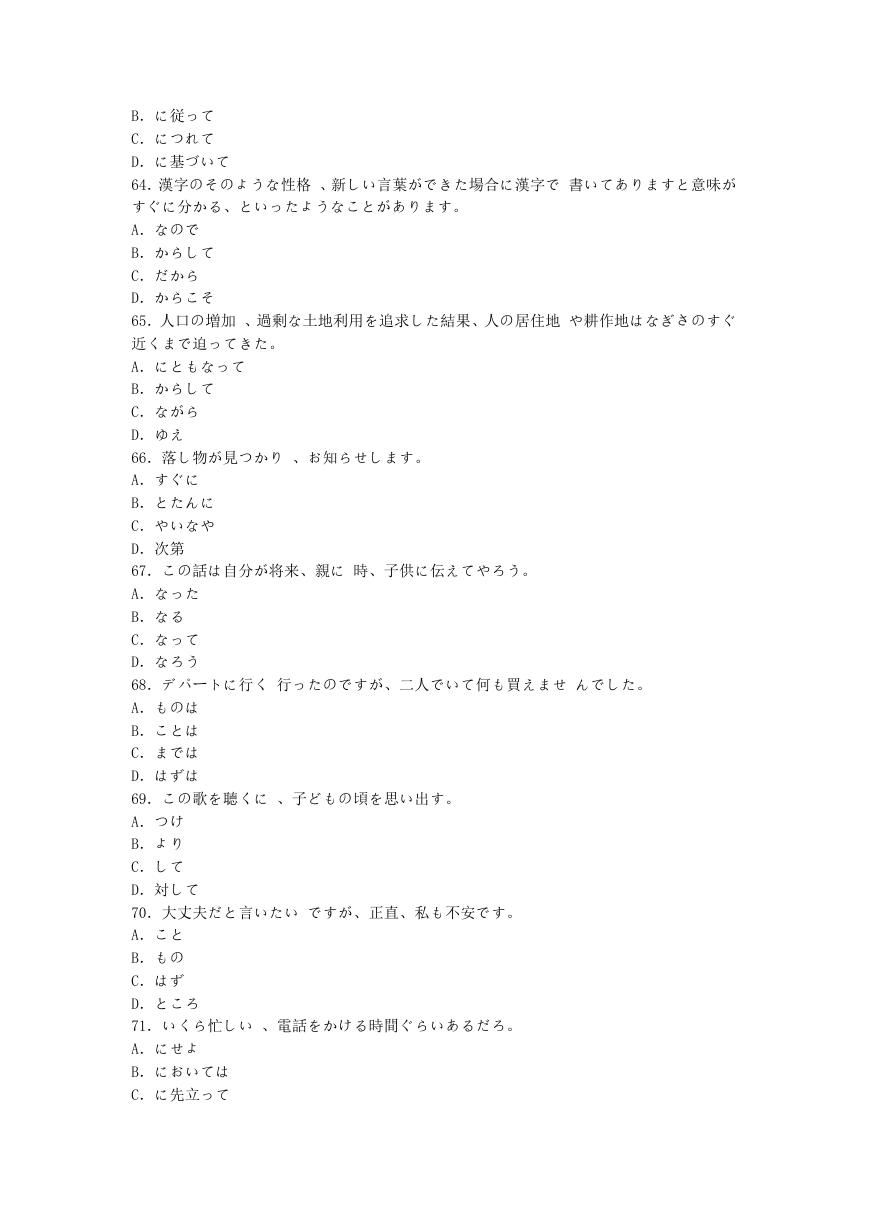
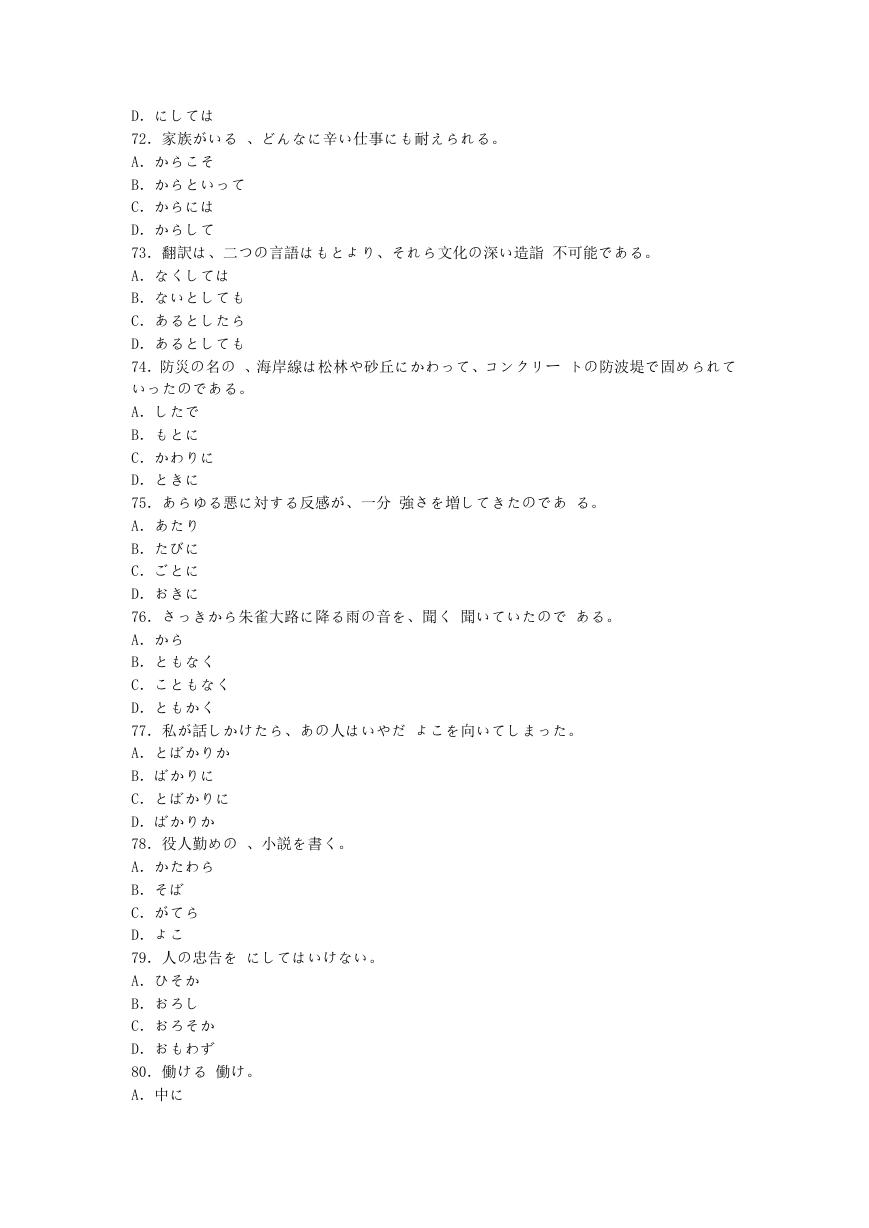
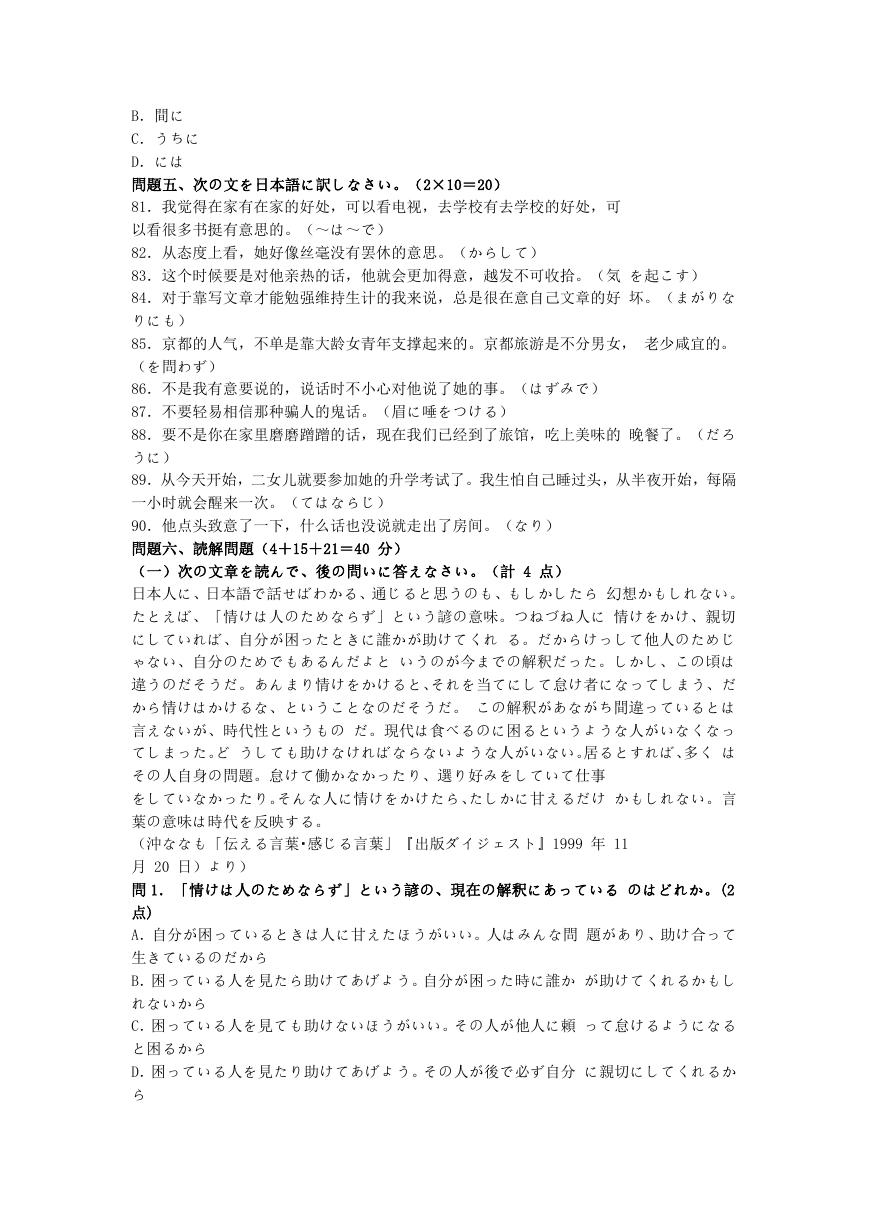
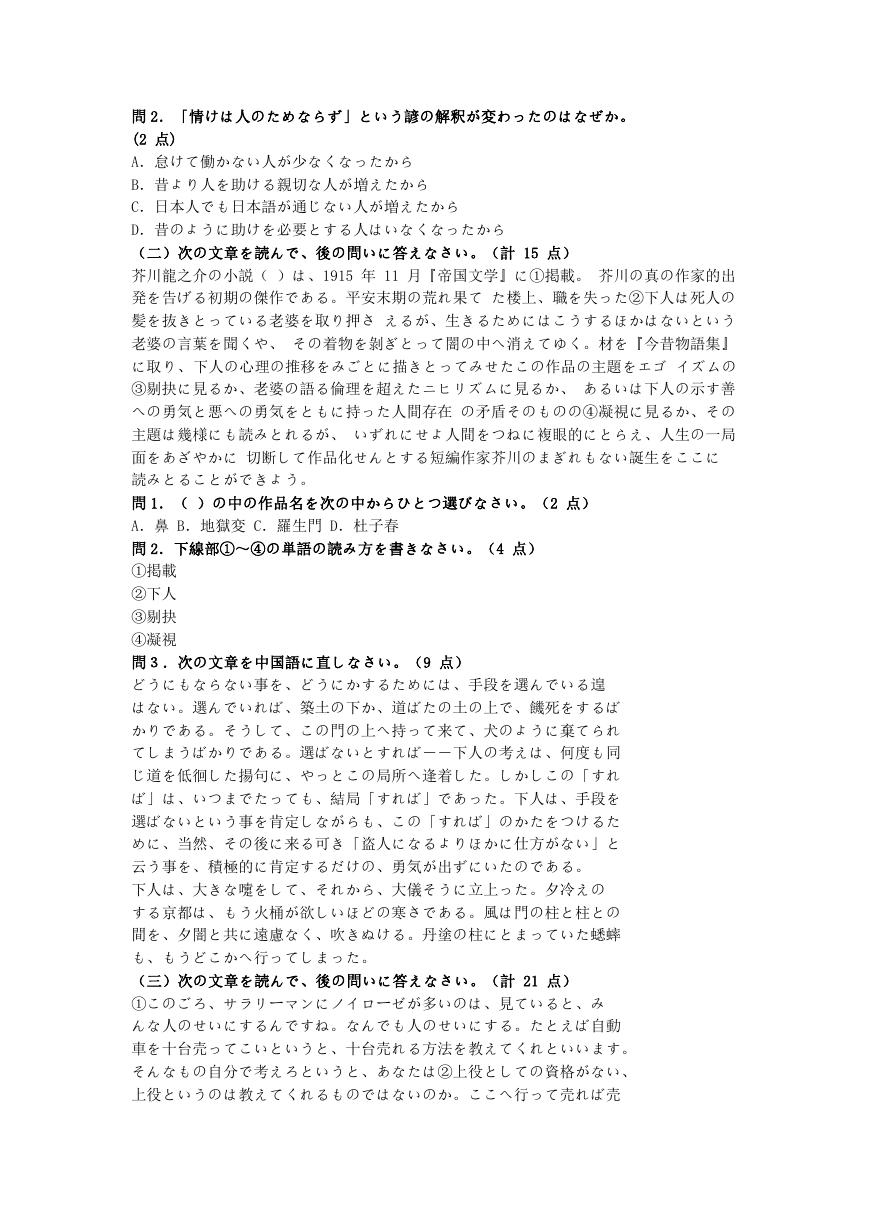
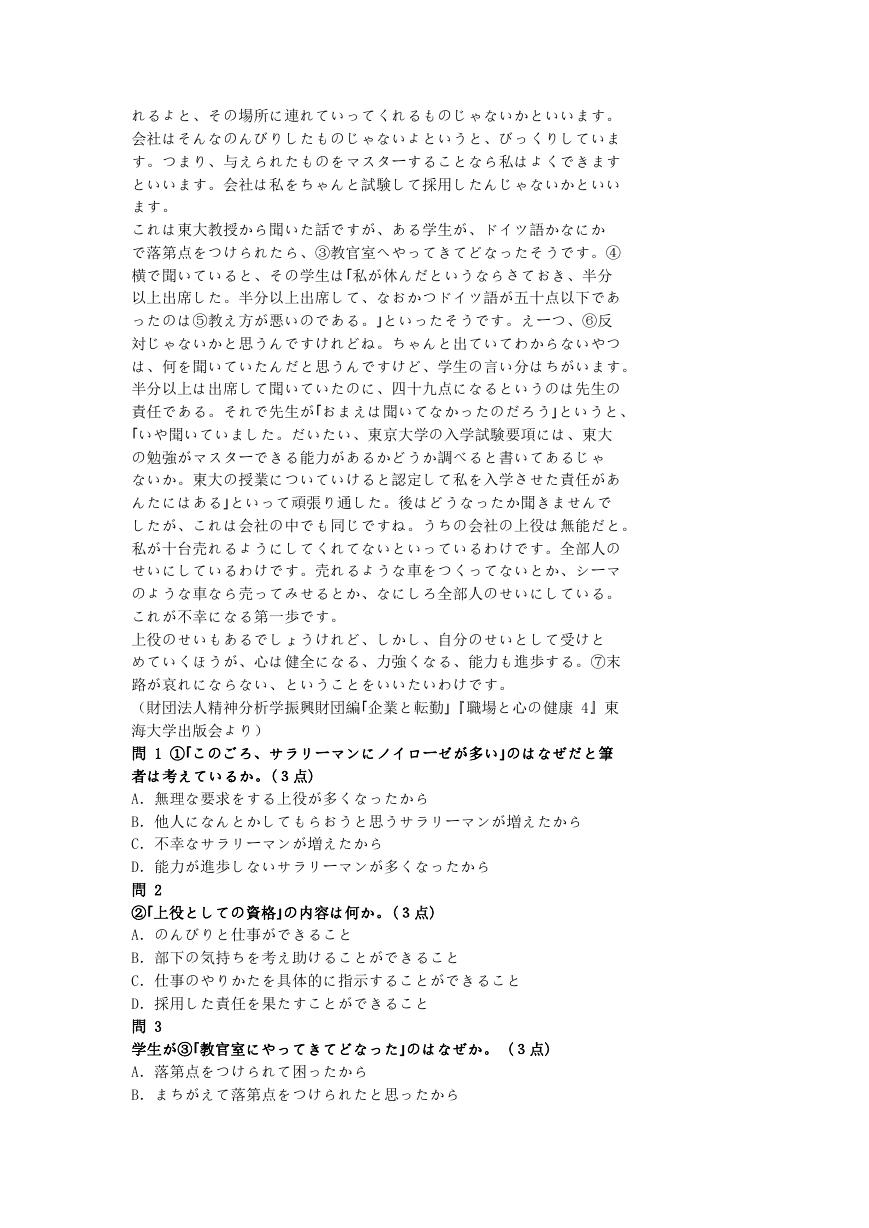
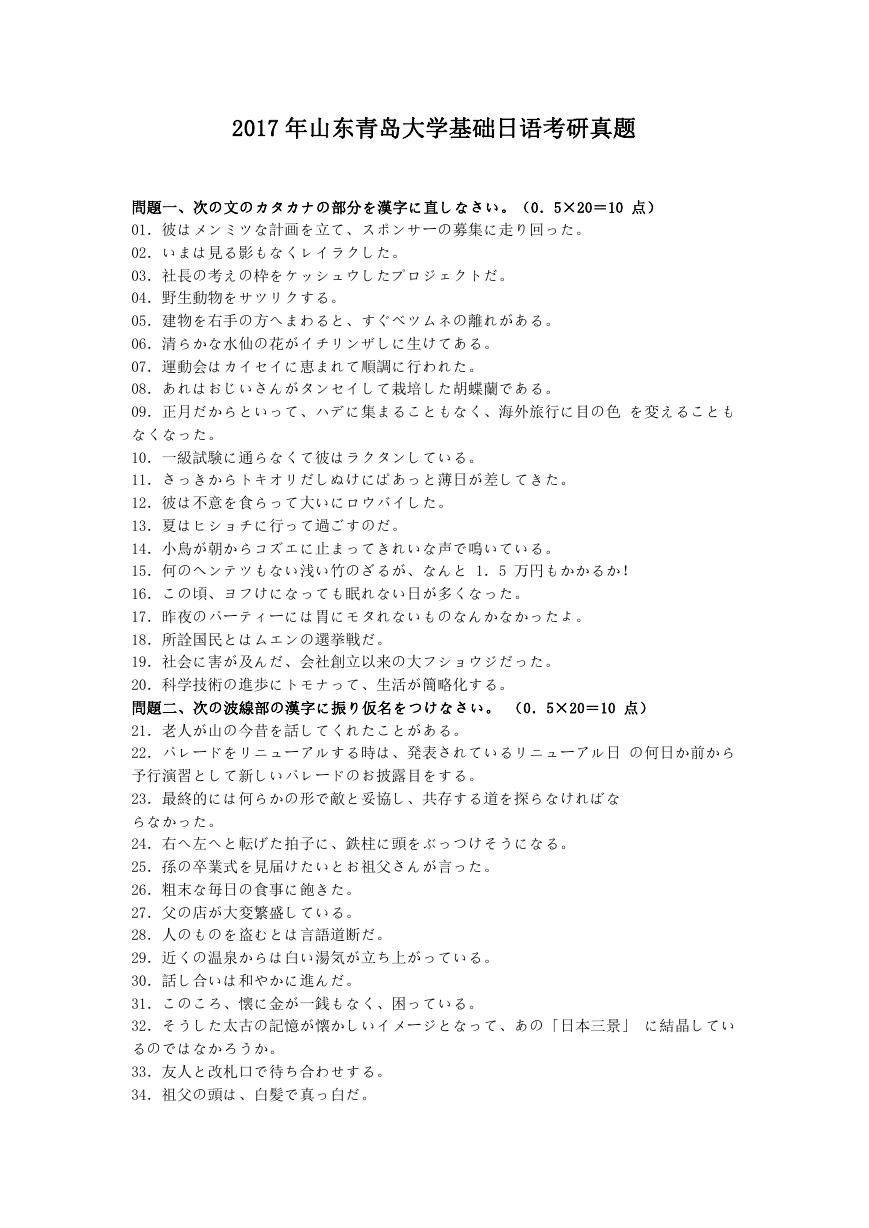
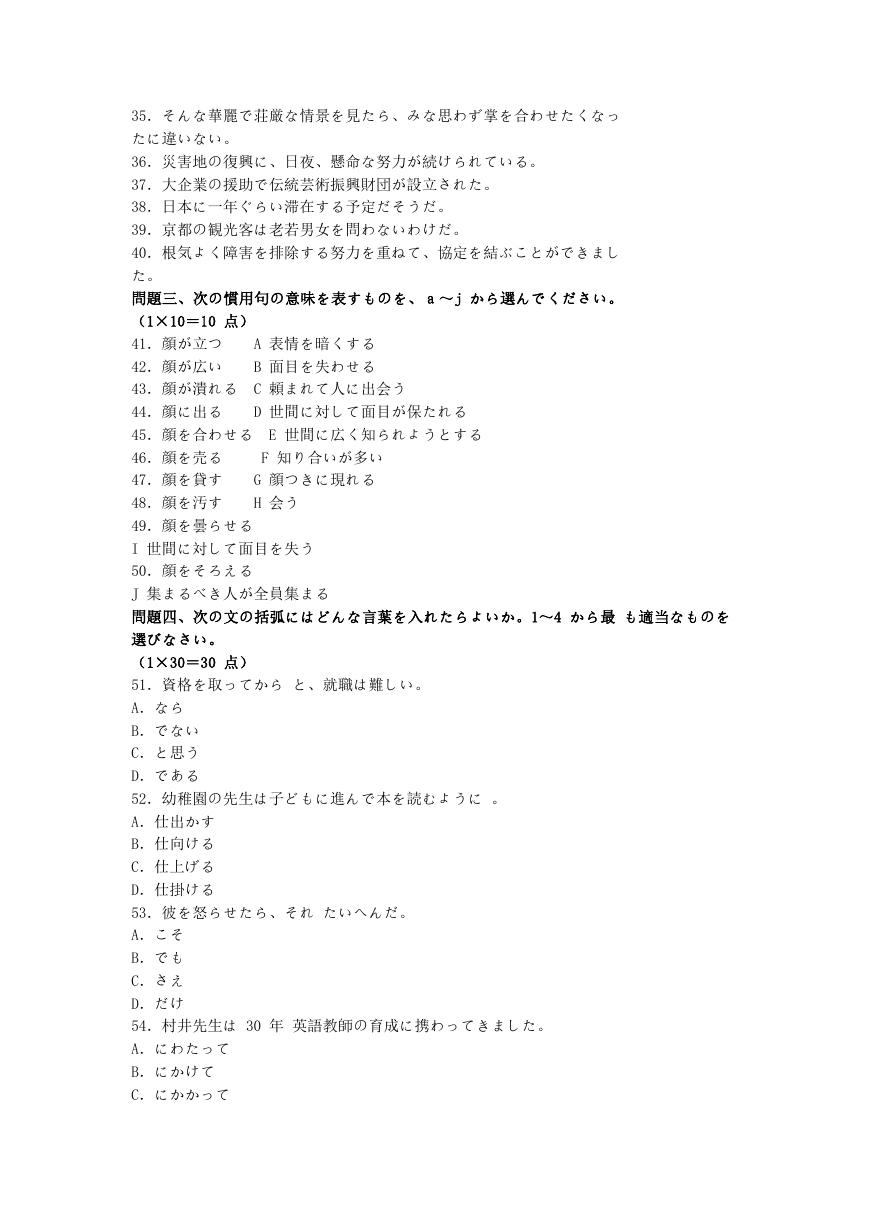
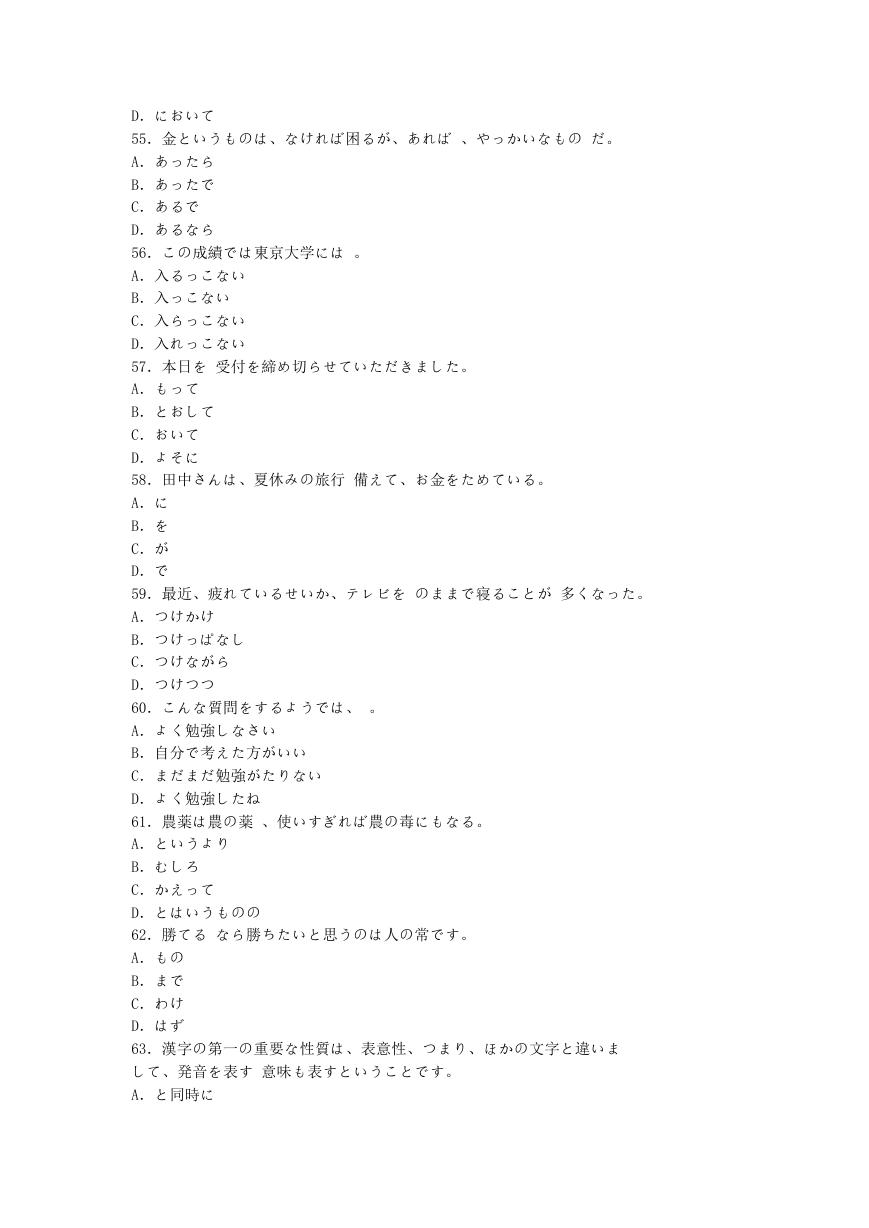
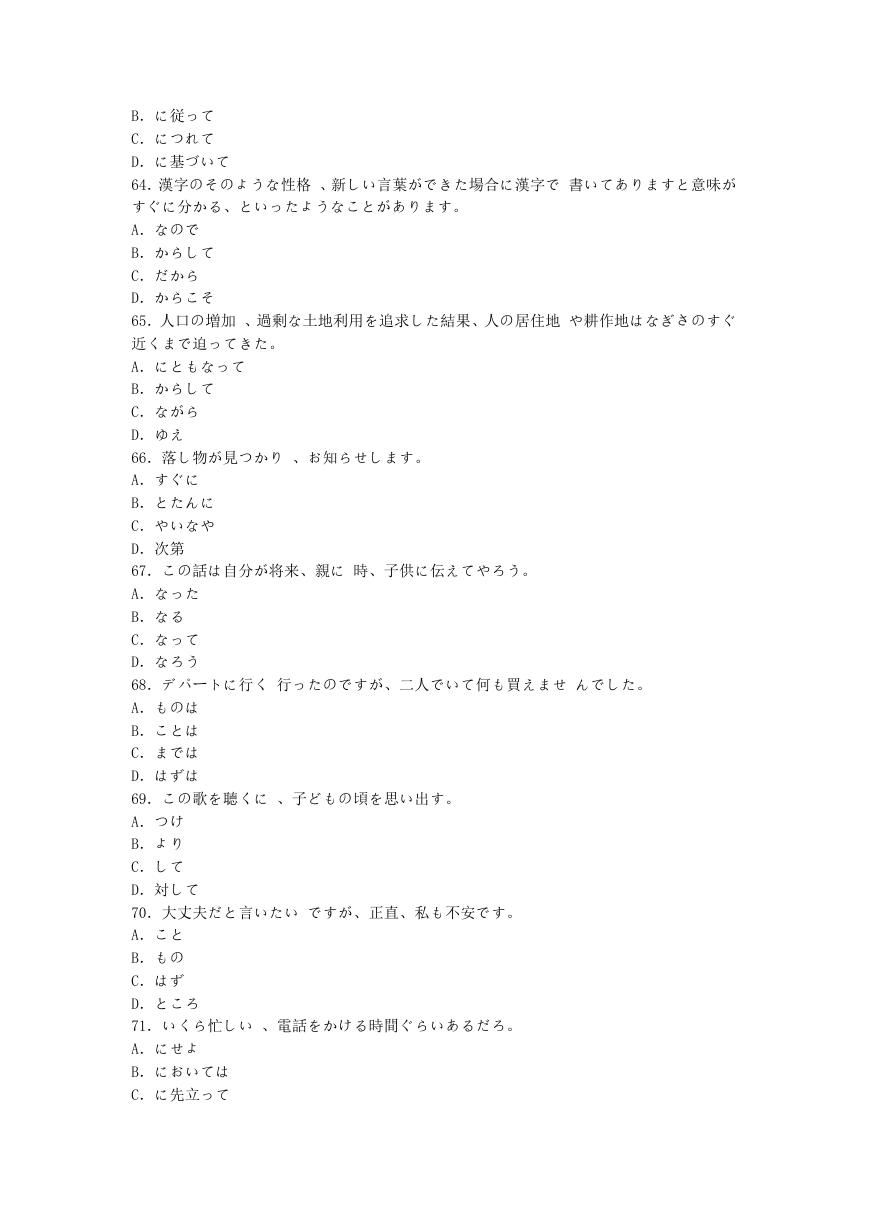
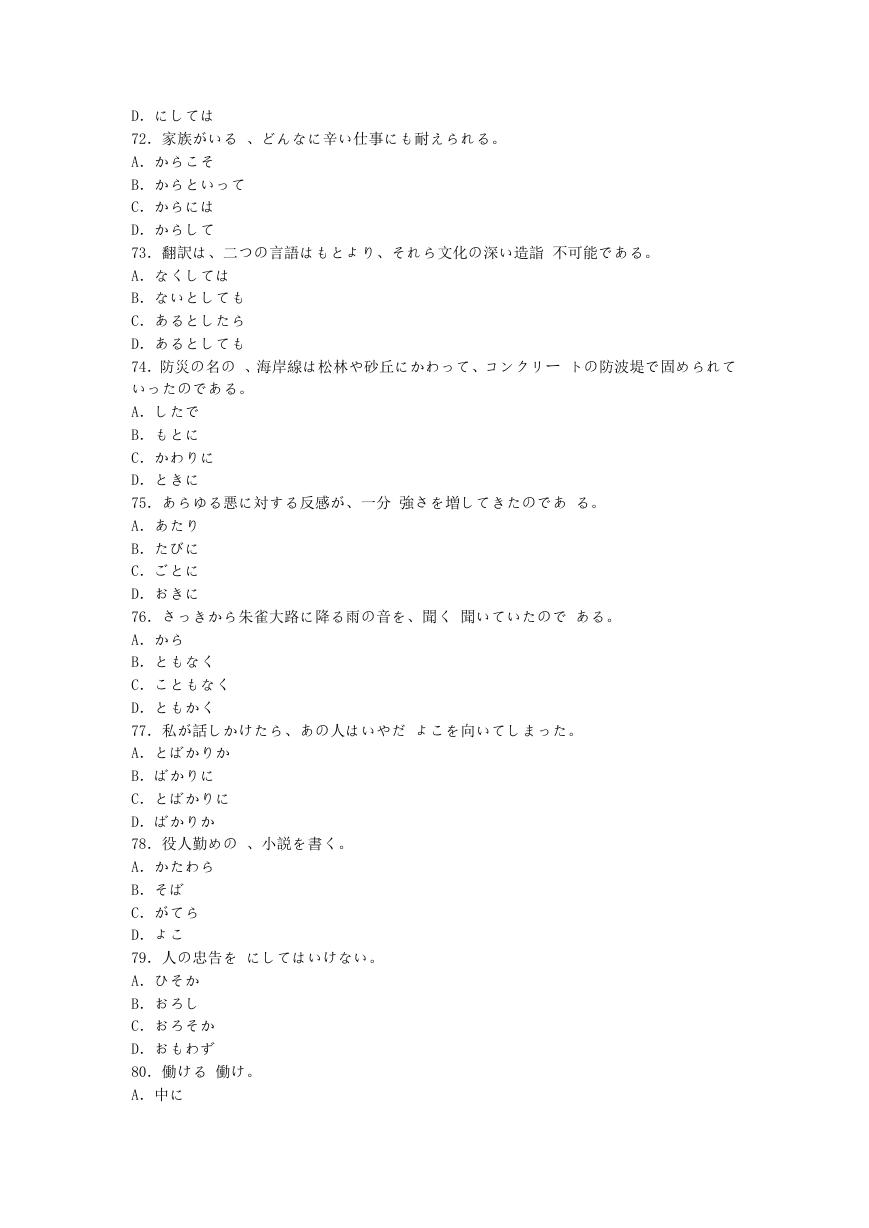
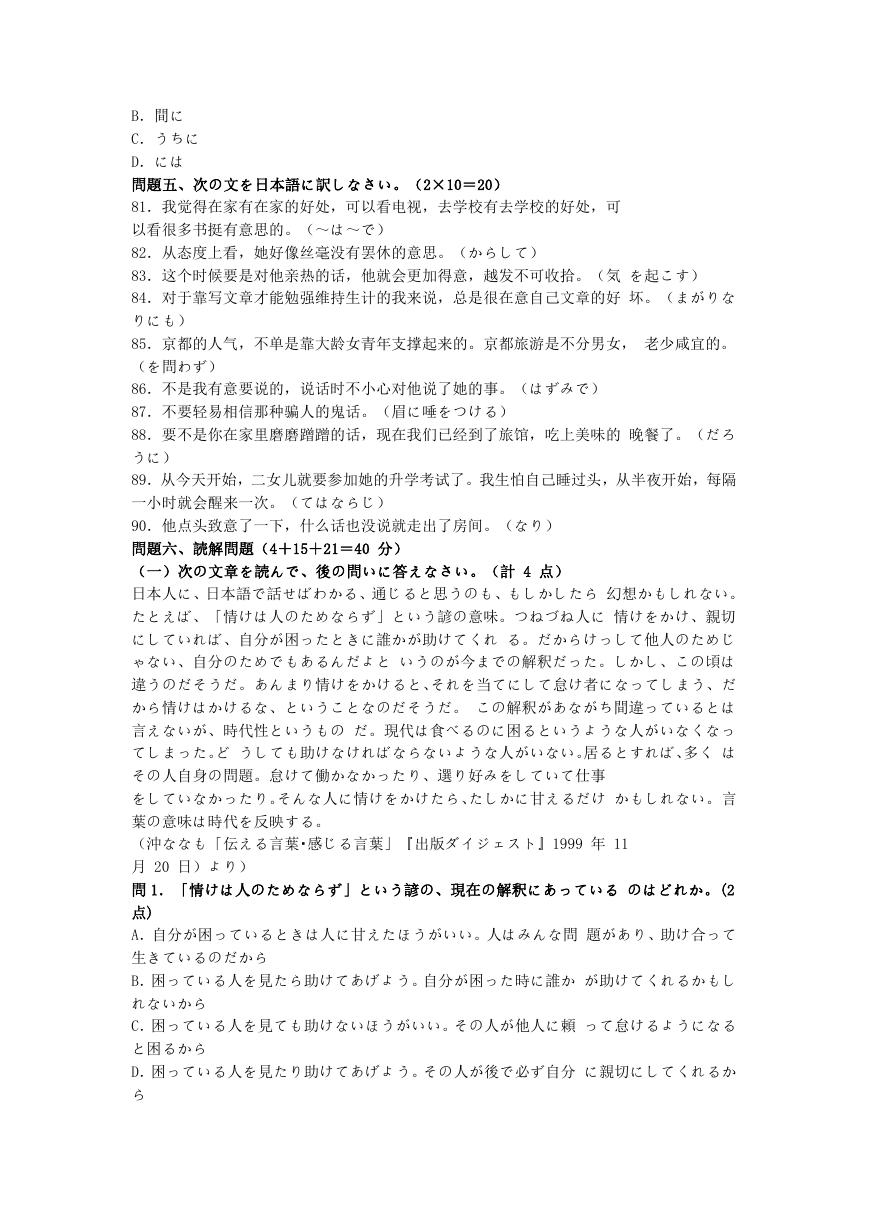
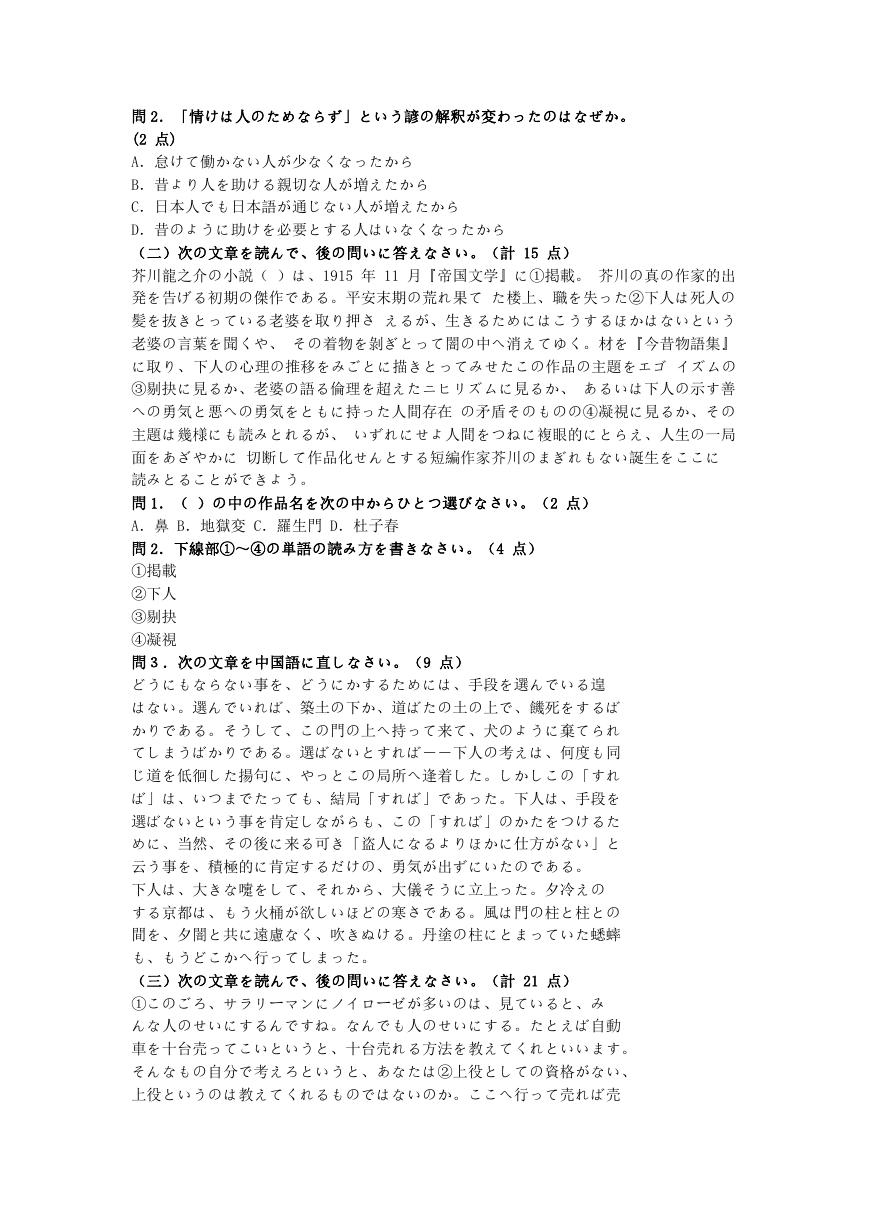
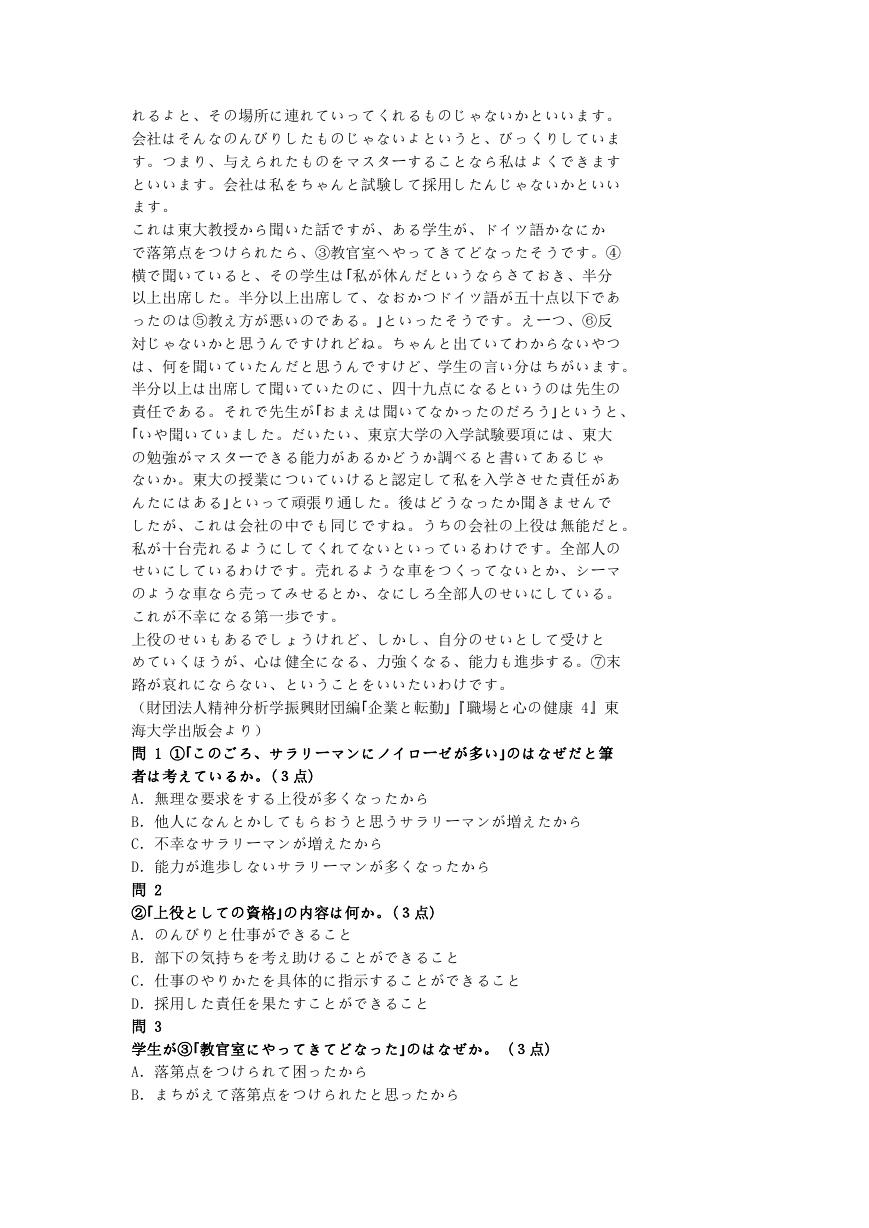
 2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc
2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc
2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc
2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc
2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc
2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc
2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc
2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc
2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc
2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc
2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc
2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc
2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc